ロングトーンのテクニック
――楽譜は書かれたりしますか?
書かないです。音楽を勉強したことがないから…実は今回のアルバムも、ギターもベースもドラムもピアノも全部僕がやっているのです。全部自宅でコツコツ一人でやっています。1曲だけバンドでやっている曲があるのですが、あとは13曲全て一人でやっていて、全部自己流の見様見真似です。
作曲をする段階でも、自分のイメージに五線紙の前で悩んだり、ピアノを弾きながら悩むということはなくて、作曲でも編曲でも出来たものが聴こえていました。楽器の編成も含めて、出来上がったものが頭の中で鳴り始めます。
よく“降りてくる”という風に、スピリチュアルな解釈で言うことがありますが、それもあるのかもしれないのですが、僕はやっぱり自分の力だと思っています。「作っているんだ」という意識があります。なので自分の好きなものしか生まれない。
自分で構築して、閃きを大事にして、それを形にするのにやっとピアノに触ると。自分の中では満足できるのですが、人に聴かせたり共有したりするには、形にしなければいけないので、「じゃあ、ピアノはこうなっているからこう弾こう、ベースはこうだからこう弾こう」という感じで録音していってから、最後に篳篥を吹くということがほとんどです。
――これは一般の方には全然参考にならないですね。
かもしれませんね。作曲で苦労をするというか、そもそも勉強をしていないので、苦労するということを通っていない。それがきっと僕流でちょうどいいのだと思います。たぶん僕がピアノをちゃんと習っていたら、相当な技術を習得したと思うのですが、きっとそういうことをしていたら、僕じゃない音楽になっていて、つまらないピアニストになっていた可能性もある訳です。
努力嫌いの勉強嫌いで、適当にやってきて「何とかする」ということできたのが、意味があったのだと思います。学校でバンドをやっていてギターを弾いて、「ギターと言えば東儀秀樹」というポジションにいましたが、他に始めたギターの仲間はもの凄く努力をするわけです。コードを覚えて、楽譜を読んで…結局、そういう人達がどんどんテクニックが付いていって上手くなっていきます。
やがてロックから始まったのが、フュージョンに行ってジャズに行って、そういうのを僕は横で見ているのですが、とても付いていけない。上手さに隔たりがどんどん出てくるわけです。僕は感覚だけで器用に「こんな感じでしょ?」というのが何となくできちゃうから、ちょっとのことで“できちゃう風”ができる。そこに人はびっくりするのですが。
――いきなりできちゃう訳ですものね。東儀さんからすると、テクニックというのは必要なものでしょうか?
何をやるか、どこを表現するか、によると思います。例えば、テクニックを表現したいミュージシャンもたくさんいて、「誰にもこの速弾きには付いてこれないだろう」というものや、「この複雑なコードどうだ!」というものも、アーティストのモチベーションだと思います。僕はそうではない、というだけです。
例えば篳篥なんて、ロングトーンだけで人を気持ち良くさせることができると思っているので、そういうことを考えると、「ロングトーンのテクニック」でもあると思います。細かい技術というよりも、もっと深い音楽感が大事だと僕は思っています。
――今は技術はありますが、一音に込める意味や魂が足りなくて、喩えるなら「びっくりショーのようになっている」「個々のスタンドプレーのようになっている」という意見をよく聞きます。
そうそう。僕は楽器屋に行くのが好きです。高校生の頃に憧れのギターを見たいというだけで楽器屋に行く感じが、そのまま続いています。楽器屋で試奏をしている子を見ていると、やたら速弾きで上手いのですが、聴いていても何にも感じない。
それよりも、技術は大したことないおじさんが「これ弾いてみていい?」と言って「キュィン!」と弾いている一音の方が凄く味があるなと感じるのは、さっきの話に通じると思います。音楽を表現したいというのは、技術を表現するということではないんだな、と感じるのです。スポーツで言ったら、ノウハウを身に付ければ絶対に高いところに行けるかといったら、そんなことはないと思います。
――ロングトーン一音だけで人を感動させるというのは、相当レベルが高くないと難しいと思います。
あとはそこに自分が「気持ち良いんだ」と思えるかというところですね。どんなにコードが変わっていこうが、同じ一音をロングトーンで吹き続けるということを僕はステージでもやるのですが、バイオリニストの古澤巌さんはいつも僕に言います。「僕にはそんな勇気はない」と。
一音だけを伸ばしていると不安でしかなくて、何か動いていないと、人に感動してもらえないのではないか、という強迫観念が昔からあるから、とにかく速く弾いたほうが人は驚いてくれることを知っているし、動かないとメロディにならないから、「東儀君みたいに一つの音で気持ち良く場をつくるということは考えられなかった」と言ってくれます。
――確かに伸ばしっぱなしは不安になるかもしれません。
でも僕は、それで人をどうにかしてやろうかという気はなくて、自分が気持ち良いだけで満足しているのが、きっと丁度いいのだろうなと思います。「人を感動させるためにロングトーンにしよう」というのだと、あざとくなってきてしまいます。
ロングトーンに限らず、一音一音、僕が責任を持ってやっているのだという気持ちがあります。音楽は絵などと違って、生まれた瞬間に消えていくじゃないですか? だから生んでいる瞬間だけが命なのだから、そこに関わっている責任というのは凄く深いと思っています。愛情だらけの瞬間なんです。
だから自分が演奏をしている瞬間の音というのが大好きでたまらないという状況が、レコーディングやステージだったりするのです。









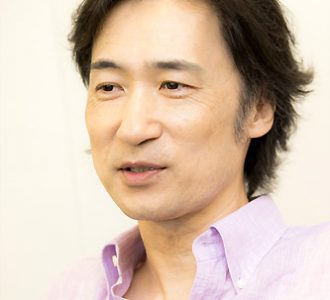




 東郷かおる子氏×東儀秀樹×ハラミちゃん、クイーンの魅力を語る
東郷かおる子氏×東儀秀樹×ハラミちゃん、クイーンの魅力を語る 東儀秀樹「ブレてなかった」変わらぬ信念とさらなる挑戦が詰まった新譜
東儀秀樹「ブレてなかった」変わらぬ信念とさらなる挑戦が詰まった新譜 篳篥に合うものを選曲、東儀秀樹 新譜で見せた自身の変化とは
篳篥に合うものを選曲、東儀秀樹 新譜で見せた自身の変化とは 東儀秀樹「大きな情熱を感じる」坂本美雨「伝えないといけない」
東儀秀樹「大きな情熱を感じる」坂本美雨「伝えないといけない」 フォルテ・ディ・クアトロ、日本への情愛示した運命のハーモニー
フォルテ・ディ・クアトロ、日本への情愛示した運命のハーモニー 意外な観点から楽しめる、語学講座のススメ
意外な観点から楽しめる、語学講座のススメ