作り手と聴き手の解釈の違いがもたらす、新たな音楽の可能性とは

ミュージシャン以外の方と、音楽の話をすると意外に興味深いことがわかったりする。考えてみれば当然なのだが、音楽の作り手が、“どう音楽を作るか”という視点にポイントが置かれがちなのに対し、聴き手は作り手が考えもしなかったような解釈をしたり、聴き方をしたりする。
近年、俳優などにインタビューをする機会が度々あり、“音楽というものとどう接しているか”ということをよく尋ねるのだが、若い俳優からは“役に入り込むためのスイッチの切り替え”という格好で音楽を活用しているという話をうかがって“ああ、やっぱり音楽にはそういう力があるのか…”などと妙に納得することがある。
また、映画監督の中には、積極的に“ミュージシャンを俳優として劇中に”と考えられている方も少なくないようだ。『SRサイタマノラッパー』などを手がけた入江悠監督は、以前インタビューで「俳優や芸人さんとは違う、ミュージシャン独自の佇まいというものがあるし、その瞬間にしか出せない色気みたいなものをミュージシャンは出せる」とその独自の雰囲気に魅せられていることを明かしていた。その他にもさまざまな監督が同じようにミュージシャンという素材に可能性を大きく感じていると聞く。
色んな人々に話を聞き、人はそういう見方をしていたのかと妙にはっとさせられるときもある。そんな自分を見返すと、別に自分は音楽を作っているわけでもないのに、考え方としてはずいぶんと作り手側によっているのだな、などと気づいたりする。そんな風にいろんな発見がある。
人はさまざまな音楽をいろんな視点で見ていることを考えると、ミュージシャン、音楽家は、自身の作るものに“音楽を作る”という思いだけを込めていては、なかなか人々の気持ちに響くものはできないのではないか、と改めて思う。
もちろん音楽は、ミュージシャン、音楽家が表現をする手段としてそこにはあるけど、単に音楽、メロディとハーモニーとリズムの塊、その3つの組み合わせだけのものから、さらに広がりを持たせていかなければならない。たとえば、役者がそれを聴いて、静かな気持ちからふっと沸き立つような激情を煽るもの、逆にどんなに笑っていても、過去にあった悲しい出来事を思わせるような深いものなど。
何度もささやかれている“音楽不況”と呼ばれる現状。私はそれを、もう新しい音楽を作ることはできない、音楽というものの限界が到来しつつある、そんな認識を持っていたが、その点については改めて考えなおしてみたい。そして、もっと音楽にできることとは何か、改めて見つめなおしてみたい、そんなことを思っている。【桂 伸也】
- この記事の写真
ありません
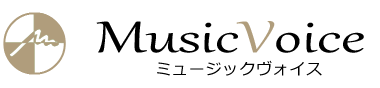
 大泉洋、大御所・柄本明にも容赦ないツッコミ
大泉洋、大御所・柄本明にも容赦ないツッコミ 入江悠監督、音楽の観点から紐解く『AI崩壊』 考える余白になった主題歌
入江悠監督、音楽の観点から紐解く『AI崩壊』 考える余白になった主題歌 大沢たかお主演「AI崩壊」リアルな近未来、AIが普及した2030年の日本社会
大沢たかお主演「AI崩壊」リアルな近未来、AIが普及した2030年の日本社会 篠田麻里子、入江悠監督は「人間の見極め方がすごい」MIYAVIの存在感引き合いに
篠田麻里子、入江悠監督は「人間の見極め方がすごい」MIYAVIの存在感引き合いに MIYAVI、加藤諒の“失言”に思わず「ぶっとばすぞ…笑」渡辺大知との乱闘シーン回顧
MIYAVI、加藤諒の“失言”に思わず「ぶっとばすぞ…笑」渡辺大知との乱闘シーン回顧 桐谷健太「僕、今感極まっています」“代表作”に出会え感無量
桐谷健太「僕、今感極まっています」“代表作”に出会え感無量 篠田麻里子の覚悟、体当たりラブシーン 鈴木浩介が感じた強さ
篠田麻里子の覚悟、体当たりラブシーン 鈴木浩介が感じた強さ 仲村トオル、弱音吐かない自主ルールも…藤原竜也の首絞めに…
仲村トオル、弱音吐かない自主ルールも…藤原竜也の首絞めに… 音楽の力で開放して欲しい、入江悠監督 感覚ピエロに寄せた期待
音楽の力で開放して欲しい、入江悠監督 感覚ピエロに寄せた期待