群馬・高崎駅に謎のポスター掲示で話題になったBOOWY、今も人気

先日、群馬・高崎駅に、BOOWYの“謎”のポスターが掲示され、ネットを中心に「復活か?」と話題を集めた。群馬と言えば、氷室京介、布袋寅泰、松井常松の出身地でもある。ところでBOOWYは、解散から30年が経とうとするのに今もなぜ人気なのか。そもそもBOOWYとはどういうバンドだったのか。
電話回線パンク
1988年におこなわれた、BOOWYのラストライブ、東京ドーム公演『LAST GIGS』(4月4日・5日)は、用意されていた9万枚以上のチケットが、発売開始たった10分で完売。予約の電話が殺到した結果、文京区の電話回線がパンクするという事態が起こったというエピソードがある。その翌月に発売された『LAST GIGS』は、ライブアルバムは異例とも言える150万枚のセールスを記録している。
解散後も人気は衰えず、1991年にリリースされたアルバム集ボックス・セット『BOOWY COMPLETE』はオリコン2位、2007年発売のベストアルバム『THIS BOOWY DRASTIC』は同5位、2008年4月5日に発売された、左記の『LAST GIGS』のライブアルバム『“LAST GIGS” COMPLETE』はオリコン10位を獲得。今もなお、再結成や復活を望む声が挙がっている。
そのBOOWYは、氷室京介、布袋寅泰、松井常松、高橋まことからなるロックバンド。当初は6人編成だった。結成は1981年、解散を発表したのは1987年、最後のライブ『LAST GIGS』は翌年の1988年。活動期間はたったの7年だ。まさに疾風の如く駆け抜け、強烈なインパクトを残した。
80年代のロックバンドにあったカッコよさ
誤解を恐れずにいえば、BOOWYというバンドは、不良で、硬派で、骨っぽい男らしさを纏ったセクシーなバンドだった。そういったロックグループはBOOWYが活躍した1980年代では決して珍しい存在ではなかった。
2017年の現在、不良っぽい色気のあるバンドというのはちょっと珍しいのではないだろうか。もしかしたら、今ではそういう感じは“ウケない”からなのかもしれない。現在、「不良」「ワル」(言葉の表現こそ古いが)といった印象で人気を博しているロックバンドは、少なくとも80年代に比べて非常に稀少だろう。
1980年代、海外のロックシーンは、LAメタルがアメリカで全盛期であったり、イギリスではパンクムーヴメントの直後で、ニューウェーヴやパブロックなど、血気盛んな音楽が蔓延し、シーンを活気づかせていた。
国内でも、80年代、90年代あたりまでは「ロックバンドの素行」として生放送で容赦なくカメラを叩き壊したり、怒りと共に唾を吐きかけたり、自らの機材を破壊したり、自傷的な流血ライブをおこなう――、といったことは決して珍しくはなかった。その時代を想起し、「今やったら怒られるじゃ済まない」と、ある種の悲観を滲ませるロッカーは少なくない。
あるミュージシャンが明かした今の風潮
本媒体がおこなった過去におこなった、ロックミュージシャンへのインタビューで、、今のロックバンドは「きれいな発言が多い」「きれいにまとめている」「きれいに売れていく」という印象を抱いている、という話があった。そして、それらは「嫌われちゃいけない」という意識が強いのではないか、ということも。それによって、「ロックバンドの“やんちゃ”な素行や発言」を暗黙の風潮で規制してしまっているのだろうか。
BOOWYが活躍した時期は1980年代。当時は、現代とは異なり、“ワル”がカッコいいという風潮が確かにあったと思われる。やや噛み砕くと、ちょっと不良っぽい方がモテた時代だったのだ。ことロックに関しては「不良の音楽」というイメージが現在よりも色濃くあったように思える。
4人編成となって1982年から6年間を駆け抜けるように活躍したBOOWYは、何者にも影響されず、“BOOWY”のまま1988年に解散した。国内ビートロックの代名詞として最初にメジャーシーンで認知されたBOOWYは、8ビートの疾走感溢れるロックンロールのスタイルを貫いた――、というだけではなく、彼らの楽曲には様々な音楽要素が散りばめられている。そのなかで、揺るぎないロックスピリットという一本筋のスタイルがBOOWYにはあったのだ。
そのスタイルとは、「不良」や「ワル」という、ある種のダークヒーロー的な存在感を、ロックサウンドで吐き出し、ロックの初期衝動、あるいは本質を、バンドの存在と楽曲で表現して貫いたということだ。
もちろん、品行方正で礼儀正しいロックバンドがいただけない、という話ではないが、BOOWYはロックのイメージを「不良」や「ワル」がキラキラと輝くその様を、「ロックのカッコ良さ」という印象のスタイルを確立した。そのなかで、反抗精神や不良の哲学は表面化させずに、あくまでを肚に抱えながら、存在と音で滲み出すようにして、決してそこを譲歩しないままメジャーシーンの第一線を走っていたように映った。
きれい事や正論、道徳的な解釈だけでは辿り着けない真実を、自身の意思で堂々とカッコ良く表現するのがロッカーという存在、あるいは「ロックだ」という事象。BOOWYはそのスタイルを最初から最後まで貫いたバンドだった。(平吉賢治)
- この記事の写真
ありません
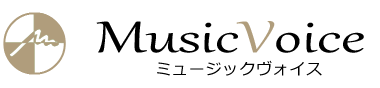
 BOOWY、結成40周年記念アナログ・シングルBOXのジャケ写&展開写真公開
BOOWY、結成40周年記念アナログ・シングルBOXのジャケ写&展開写真公開 BOOWY、結成40周年記念Special Photo Book発売決定
BOOWY、結成40周年記念Special Photo Book発売決定 BOØWY「LAST GIGS」2DAYS、初の全曲収録へ メモリアルリリース最後
BOØWY「LAST GIGS」2DAYS、初の全曲収録へ メモリアルリリース最後 【結果】日本のロックの聖地といえば?
【結果】日本のロックの聖地といえば? 布袋寅泰、BOOWY時代の写真投稿、氷室からマイクを向けられる姿
布袋寅泰、BOOWY時代の写真投稿、氷室からマイクを向けられる姿 布袋寅泰「眉毛なし」17歳の写真に反響、超レア BOOWY結成前夜
布袋寅泰「眉毛なし」17歳の写真に反響、超レア BOOWY結成前夜 「THANKS BOOWY」ファンら朝日新聞に広告、感謝の思いを伝える
「THANKS BOOWY」ファンら朝日新聞に広告、感謝の思いを伝える BOOWY、最新映像作品を見て感じたもの 浮き上がる真の解散理由
BOOWY、最新映像作品を見て感じたもの 浮き上がる真の解散理由