氷室京介「LAST GIGS」を振り返る、万感ラストへ繋がった各公演

氷室京介
氷室京介とは何か――。自身初のオールキャリア・ベストアルバム『L'ÉPILOGUE』で問うたテーマだった。顧みて、ライブ活動無期限休止前最後の4大ドームツアー『KYOSUKE HIMURO LAST GIGS』は、全7公演それぞれにドラマがあり、そこには必ず氷室京介の“生き様”があった。
4月23日の京セラドーム大阪で始まり、その1カ月後の5月23日、東京ドームでその幕は閉じた。全7公演。どれも記憶に残る凄まじいライブだった。とりわけ、東京最終日はこれまでに見たことがない光景が広がっていた。ステージ裏までびっしりと埋まった5万5000人の観客から発せられる、一糸乱れぬ歓声と手拍子。それに呼応する氷室京介の歌声とバックバンドの演奏は、互いに刺激し合って凄まじいグルーヴを生んだ。まさに日本音楽界の最高峰と言っても過言ではないライブだった。
しかし、あの奇跡的な空間を実現させたのは、涙を流した東京初日や二日目の盛り上がりがあったからこそ。更に言えば、東京公演は、満身創痍で届けられた福岡、神がかり的なグルーヴだった名古屋、そして、“再会”と“最後”の心情が複雑に絡み合った初日大阪が無ければ有り得なかった。言わば、どれが抜けてもあのステージは成り立たなかった。
それぞれに意味があった7公演
大阪公演は、1年半ぶりに氷室のライブを体感できる嬉しさと、これが最後のライブであるという悲しみの感情が複雑に絡み合った。あの横浜スタジアム最終公演と同様、雨がパラついた大阪初日は、MCをほとんど挟まずに本編25曲を熱唱。「Dreamin'」で始まり、「RUNAWAY TRAIN」「BLUE VACATION」とBOØWYの楽曲が続いた。この流れは2011年におこなわれた、東日本大震災復興支援チャリティライブ『KYOSUKE HIMURO GIG at TOKYO DOME “We Are Down But Never Give Up!!”』を彷彿とさせた。
そして、中盤からは重厚なロックにリアレンジされた「LOVE & GAME」が届けられ、その後はBOØWY曲を挟んでのソロ曲を届けていく。アンコールでの「REVORVER」「KISS ME」「IMAGE DOWN」という流れは大阪初日だけの構成。当然、会場は高揚感に包まれた。
セットリストの半分がBOØWY楽曲。それらをノンストップで届ける姿勢をその頃は、最後のステージは「氷室京介」のキャリアを、“本筋”である楽曲だけをもって示す考えなのであろうと汲んだ。ただ、ラストライブだからこそソロ楽曲をより多く聴きたかったという声も一部であった。そうしたそれぞれの想いと歓喜、悲しみが交差したのが大阪初日であり、2日目もほぼ同様だった。
神がかり的なグルーヴが生まれた名古屋
大阪に対して、名古屋公演は凄まじいものがあった。Charlie Paxsonのドラム、西山史晃のベースサウンドが全体的に前に出ていて、音の骨格がしっかりとし、サウンドを押し上げていた。大島俊一のキーボードもそれに乗り、ドラマチックな音色が彩った。そして、YTの自由自在で優雅なギターグルーヴが踊り、忠実で丁寧なDAITAのギターもこの日は規律性の上で激しく舞ってみせた。
そうしたサウンドの上で映える氷室京介の歌声は魂が込められ、力強くも繊細で圧巻だった。大阪よりも、曲が進んでいくピッチが速くなっている分、ライブ全体のグルーヴが増していた。まさに神がかり的なステージ。とりわけ、大阪では本編ラストを飾っていた「ANGEL」からの「SUMMER GAME」という流れは鳥肌が立った。
この神がかり的なグルーヴが生まれるのも当然で、氷室はMCで、名古屋を第二の故郷と讃えた。恩人が名古屋にいて「BOØWYがデビューした時もその人で。その人の紹介がなかったらBOØWYも誕生していなかったし、氷室京介としての俺もいなかった。本当に恩人。キャリアを辞めるという話をした時も俺にダメ出しを言ってくれて、シビアなことを言ってくれた人。その人に恥ずかしくないように頑張ってきた」と語った。その恩人に無様な姿は見せられないという想いが形となって表れていた。
言葉で想いを伝えた福岡
一方で、大阪と名古屋に対しての福岡公演は、今回のツアーのなかでも異色だった。氷室は、これまでMCを挟まずにノンストップで曲を届けたセットリストに触れ「皆は最後のライブで覚悟してきているのに、一方的に歌い届けてしまって」と自省。MCに大きく時間を割き、リベンジマッチを誓った一昨年の横浜スタジアム公演の裏話や現在の心境などを包み隠さずに、言葉をもってその思いを届けた。
楽曲によって細かくテンポやアレンジを変え、一小節一小節を噛み締めながら歌い届けた。同じ楽曲であってもこの日はまたその趣は異なっていた。BOØWY時代の楽曲はこれまでの3公演とは異なり、当時の“氷室京介”が完全に蘇っているようだった。今の氷室でありながらも歌声や歌い方は当時の氷室に近く、若く艶やか。それは時折アグレッシブなプレイを入れながらも忠実にオリジナル感を再現する演奏も重要な役割を果たしていた。
しかし、楽曲が進んでいくなかで、氷室の体調に著しい変化が見られた。明らかに不調の耳を気にしている様子。これまでの公演でも耳を気にする様子はあったが、この日は少し違った。最後の方にはイヤモニを外して歌う姿もあった。この日は、ツアー中最も少ない本編22曲。かろうじてアンコールに応えるも最後はスタッフに抱えながらステージを後にした姿が強く印象に残った。
福岡のように、ツアー中は体調の悪いと思われる姿が何度かあった。しかし、その時は決まってバラード曲の説得力がずば抜けていた。いつもながらに増して気迫みなぎるソロ楽曲のバラード。鬼気迫るその歌声で届けられる言葉の一つ一つは、観客の心を、時に鋭く突き刺し、時に優しく撫でた。身は朽ちても魂で歌い届ける、そんな気骨が垣間見えた。まさに満身創痍だったが、そこには氷室の生き様があった。
氷室がみせた最初で最後の涙
そうしたなかで迎えた東京公演。体調を心配する声もあったものの、蓋を開けてみれば思い過ごしだったと感じる。調子も良く2度のアンコールに応えた。バックバンドはオリジナルアレンジに忠実ながらもそれぞれの個性で色を付けて彩った。そして、ファンのエネルギーも凄まじかった。
急きょステージバックに設けられたリアルライブビューイング席。当然、氷室の姿はスクリーンでしか確認できないが、そんなのはお構いなし。大歓声をもって楽しんだ。そんな姿に氷室は体をそちらに向けて叫んだ。「あそこだけライブハウスみたいだな」と上機嫌だった。
ファンのアグレッシブな反応に笑顔も自然とこぼれるも、アンコールラストの楽曲「SUMMER GAME」で氷室は感極まって歌えなくなった。しかし、それをファンが大合唱して歌い紡ぎ、支えた。その姿にDAITA、そして長年連れ添った西山も涙ぐんだ。
ラストに見た悲しみは東京2日目、そして東京最終日で一層深くなるものと思った。しかし、そうではなかった。まず、東京2日目もノリは変わらず、むしろ悲しみの一切を前日に吐き出したかのようにスッキリとした表情だった。そうした過程で迎えた最終公演。氷室は「体調が良い時と悪い時がある。聴きづらいかもしれないけどゆっくり楽しんで」と語った。その言葉には人間味があふれていた。
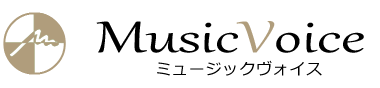




 氷室京介「LAST GIGS」東京初日が映像作品化される意義、唯一涙を流した伝説の公演
氷室京介「LAST GIGS」東京初日が映像作品化される意義、唯一涙を流した伝説の公演 氷室京介、ソロデビュー35周年を記念した映像BOXを発売
氷室京介、ソロデビュー35周年を記念した映像BOXを発売 氷室京介、ソロデビュー35周年を記念したイベントが決定
氷室京介、ソロデビュー35周年を記念したイベントが決定 氷室京介、ソロデビュー記念日に未公開ライブ映像を配信
氷室京介、ソロデビュー記念日に未公開ライブ映像を配信 氷室京介、ソロデビュー33周年を記念した映像配信が決定
氷室京介、ソロデビュー33周年を記念した映像配信が決定 田家秀樹×山崎大介、クロストークイベント「氷室京介を探して」11月15日開催
田家秀樹×山崎大介、クロストークイベント「氷室京介を探して」11月15日開催 田家秀樹氏が氷室京介を語るインタビュー映像を配信
田家秀樹氏が氷室京介を語るインタビュー映像を配信 氷室京介、サブスク解禁 記者が早速体験
氷室京介、サブスク解禁 記者が早速体験