2016年に行われた氷室京介の4大ドームツアー『KYOSUKE HIMURO LAST GIGS』の東京初日公演が、氷室京介ソロデビュー35周年記念映像作品『KYOSUKE HIMURO 35th Anniversary LIVE FILMS AND PHOTO BOOK Quod Erat Demonstrandum』に完全収録される。ツアー最終日はすでに映像化されているが、氷室が唯一涙を流した東京初日を、大阪・名古屋・福岡公演の厳選映像と共に収録されるのは意義深い。タイトル「Q.E.D」に込められた「証明されるべきもの」のごとく、氷室が歌い続けてきた証しが刻まれる。【文=木村武雄】
映像のなかで歌い続ける氷室京介
2016年5月21日。東京ドームは熱気に包まれていた。「最後の夜だぜ!騒ごうぜ!」。この瞬間、歓声がドームを揺らした。程なくしてイントロが始まる。「DREAMIN'」。再び割れんばかりの歓声が轟いた。あれから7年が経っているのに、映像の中の氷室は生き生きとしている。初めて体感するかのような感動が押し寄せ、あの時と同じように涙が込み上げてくる。モノクロになりつつあった記憶が鮮明に色づいていく。
「矜持」(きょうじ)―。
「無様でも立ち上がればそれが生き様になる、そう思い歌い続けてきた」氷室京介が自身を表現するものとして使った言葉だ。以来、「矜持」は特別なものになった。この言葉を耳にすればあの光景が思い出されるし、自身を鼓舞する言葉になっている。彼の生き様がこの字に宿っている。
矜持の「矜」は、「矛の柄」が語源という。古代中国の武士にとってそれを持つことは誇りであり、それを持ち続けることはまさに「プライド」。その「矛」に連なるのは「今」。この「今」という字にも氷室が体現されていると、この映像作品を観て気づかされる。その時代その時代を氷室は映像のなかで「今」も歌い続けている。そう、時を刻んでも全く色あせないのである。
「今」が積み重なって「今」を構築する。それは『KYOSUKE HIMURO LAST GIGS』にも表れている――。
各公演が作った東京初日
ラストツアー初日となった大阪2DAYSは、1年半ぶりの再会といよいよ終わりを迎える悲しみが複雑に絡み合い緊張感が感じられた。氷室も「みんなも覚悟して来ているのにどう向き合えばいいか戸惑ったと思う」と後に振り返っている。リハーサルではステージを下りて照明をチェックしたり、モニターや音の反響、ハウリングなど、機材を“愛車”を扱うように微細にチェックする姿が印象的だ。本編からは大阪2DAYSのみの「ダイヤモンド・ダスト」や大阪初日のみの「REVOLVER」が収録されている。
名古屋公演は大歓声が生んだ神がかりなグルーヴ感が印象的だったが、映像でものっけからそれが伝わってくる。名古屋と東京最終日だけの「VIRGIN BEAT」、そして「SEX & CLASH & ROCK’N ROLL」の貴重映像も収録されている。
そして気になっていたのは福岡公演だ。アンコールを満身創痍で臨んだ氷室は最後、スタッフに抱えられながらステージを後にした。だが開演前はYTと談笑するなど大阪、名古屋と比べてもリラックスしている様子が映し出されている。その状態からいかにしてラストへと向かったのか。どの公演もバラードは圧巻だったが、特に福岡公演は這ってでも届けるという覚悟からの鬼気が漲っていた。今回は残念ながら収録されておらず今後の完全収録化を期待するところだが、「BEAT SWEET」「PLASTIC BOMB」「WILD AT NIGHT」、そして本編ラスト「WILD ROMANCE」の流れは地続きで収録されていて、笑顔に隠れるその生き様が垣間見える。
そして迎える東京ドーム初日――。
特別な意味を持った東京初日
ラストツアーはまるで氷室京介の半生を凝縮したかのようだった。全公演にストーリーがあり、生き様があった。どれが抜け落ちても「LAST GIGS」とは呼べない。氷室自身もツアーに臨む前に「7公演全てを通して一つの『LAST GIGS』なんだ」と語っていた。
なかでも東京初日は特別な意味を持っていた。
MCでは、ベースやギター、打ち込み機材を買って初めてデモテープを作ったBOØWYの『JUST A HERO』にも触れた。当時のメンバー間の様子やこのアルバムがなければ「今」の自分はないとも語った。そこからの「WELCOME TO THE TWILIGHT」。氷室はほんのり涙目になっていた。映像だからこそ微細な感情の揺れ動きが伺える。
この初日は「WELCOME TO THE TWILIGHT」を起点に「ミス・ミステリー・レディ」「"16"」「LOVE & GAME」「IF YOU WANT」「LOVER'S DAY」「CLOUDY HEART」からの「PARACHUTE」「WARRIORS」「NATIVE STRANGER」の流れが心を震わせた。氷室も「BEAT SWEET」を届けた後「気持ちいいぜ!東京ドーム!」と笑顔だった。
終盤、埋め尽くされた約5万5千人を前に氷室はこう言った。「35年間みんなのおかげで大好きな歌を歌ってこられた。まだ明日も明後日もあるけど辿り着きたい場所に辿り着けたかなって。そういう気持ちです」。達成感に満ちた晴れやかな表情だった。
全ての始まりは「ANGEL」だった。ソロになった1988年、狼煙を上げるように発表されたシングル「ANGEL」、そしてアルバム「FLOWERS for ALGERNON」。その年の「日本レコード大賞」で金賞とアルバム賞を受賞。その翌年には東京ドーム公演が開かれた。後に「Sanctuary」となる東京ドーム公演はこの年に始まった。その「Sanctuary」の結びに、ラストツアー東京初日の本編最後に「ANGEL」を歌った。最後に相応しい曲だった。過去の幾多の記憶が走馬灯のように脳裏を駆け巡った。
そして、アンコールではメンバーを丁寧に紹介した。ステージ袖にいるマニュピレーターのTesseyは今にも涙が溢れ出そうだった。「そろそろ花も散って夏を迎えるこの季節に最後にこの曲を贈りたい」と初日ラストは「SUMMER GAME」。目の前に広がる約5万5千人の観客を観て涙で歌えなくなった氷室の代わりにファンが歌った。その声は音をも凌駕するほどでこれまでに見たこともないすさまじい光景だった。大きく口を開けて歌うベースの西山史晃も映し出された。氷室は涙を押し殺すにはもう叫ぶように歌うしかなかった。まさにすべてを出し切った。それが映像からはっきり伝わってくる。
各地で繰り広げたドラマがこの初日に帰結したことを示していた。2日目、最終日は悲しみを全て放った後の「最後の宴」とも言うようにすっきりとした表情で楽しんでいるようだった。
そのことを裏付けるものが本作収録のメイキング映像にある。ツアー初日となった大阪公演、ステージに上がる前、氷室は「感傷的になっている時間はないと思うよ」と笑いながら話した。ラストツアーではあるが、ドームを熟知している氷室でさえ“ドームの魔物”がどううごめくのか予想ができない。そんな戦いでもあったことに気づく。

KYOSUKE HIMURO 35th Anniversary LIVE FILMS AND PHOTO BOOK Quod Erat Demonstrandum
「今」を歌い続けている
ある映像ディレクターが、氷室は動きでも音を表現していると言った。もちろん音も大事だが、たぎる力を、歌声、音、そして体で表現するのがロック、いやそれこそがヒムロックなのであろう。
その生き様こそが、映像の中で生きさせている証とも言える。
今回収録されている「Birth of Lovers -1990.10.07 GREEN DOME MAEBASHI-」もしかり、「BEAT HAZE ODYSSEY-2000.11.07 YOKOHAMA ARENA-」も全く色あせない。それはその瞬間瞬間を満身創痍、全身全霊で向き合ってきた氷室だからこそ、その躍動は映像になっても全く抜け落ちない。むしろ映像の中で進化し続けているとさえ感じる。
映像のなかの氷室は「今」も歌い続けている。観る者の手を引くようにその時代へと誘い、まるで「今」起きているかのような生き生きとしたリアリティで包み込んでくれる。
色あせない躍動。止まらない脈動。「矛」と「今」。それが氷室の象徴であり、それがこの映像作品で証明されている。メンバーやスタッフ、そしてファンとの信頼関係の上に立つ感動。映像に映る一つひとつの言動が「今を生きる氷室京介の生き様」の証なのである。
【氷室京介Q.E.D特設サイト】
https://sp.wmg.jp/kyosukehimuro35th


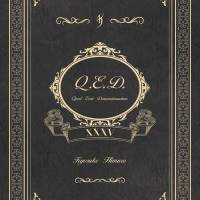
 氷室京介、ソロデビュー35周年を記念した映像BOXを発売
氷室京介、ソロデビュー35周年を記念した映像BOXを発売 氷室京介、ソロデビュー35周年を記念したイベントが決定
氷室京介、ソロデビュー35周年を記念したイベントが決定 氷室京介、ソロデビュー記念日に未公開ライブ映像を配信
氷室京介、ソロデビュー記念日に未公開ライブ映像を配信 氷室京介、ソロデビュー33周年を記念した映像配信が決定
氷室京介、ソロデビュー33周年を記念した映像配信が決定 田家秀樹×山崎大介、クロストークイベント「氷室京介を探して」11月15日開催
田家秀樹×山崎大介、クロストークイベント「氷室京介を探して」11月15日開催 田家秀樹氏が氷室京介を語るインタビュー映像を配信
田家秀樹氏が氷室京介を語るインタビュー映像を配信 氷室京介、サブスク解禁 記者が早速体験
氷室京介、サブスク解禁 記者が早速体験 布袋寅泰、氷室京介の第一印象は「目がカッと鋭くて…近寄りがたい」
布袋寅泰、氷室京介の第一印象は「目がカッと鋭くて…近寄りがたい」