無音は強烈な効果、無音を意識すると音楽の捉え方も変わる?

圧力の力を電気に変えるピエゾ素子というものがある。何年か前に、それらを活用したシステムを道路に埋め込むことで街灯の電気をまかなうという話があった。また製造界では、ものを作るときに、わずかな電気の違いを読み取って品質維持に役立てる製品も出ている。楽器のチューナーなどもこれらの仕組みを利用したタイプも出ている。
さて、ここのコラムでは最近、“無音”がテーマに上がることが多い。この無音だが、作曲家・芥川也寸志さんの著書『音楽の基礎』(岩波新書)には、真の静寂は日常生活には存在しない特殊な環境であるが、音楽における無音、つまり休止は最強音にもまさる強烈な効果を発揮するとしたうえで「音楽は静寂の美に対立し、それへの対決から生まれる」とし、「音楽の鑑賞にとって決定的に重要な時間は演奏が終わった瞬間、つまり最初の静寂が訪れた瞬間である」と、無音があって初めて音楽は成り立つということが綴られている。
また、ピアニストで作編曲家の小曽根真さんは小媒体のインタビューでこういうことを語っていた。「無音も演奏するんです。だから『休符』という表現は間違っています。休んじゃ駄目なんですよ。休符があったときにオフになってしまったら、楽しくない。自分が次のフレーズを吹くのに、今のフレーズを聴いてないとできないはずです」と。
古代ギリシアの数学者であるピタゴラスが提唱した理論に「天球の音楽」というのがある。宇宙では全ての物質が重なり合って音が出続けているいわば、宇宙全体が音を奏でている。しかし、これらは常時存在しているので我々は気づいていないというものだ。雑な言い方をすれば、その音に“慣れ”が生じているため、感覚的には聴こえていない。
ヒトの記憶について興味深い話があった。ある評論家は、人の印象は最初にみた記憶がベースにあり、二回目に会ったとしても目の前にいる情報ではなく、最初に会った情報で処理していると。つまり、何度会っても最初の記憶しかその人物を判断していない。よって人の記憶ほどいい加減なものはないと。
さて、物質と物質がぶつかりあい、こすり合い音が発生する。声もそうだし、楽器もそうだ。しかし、「天球の音楽」によれば一定の音は気づかないこともありえる。それは実際の日常にもある。例えば、無関心もそうだし、他の情報の印象が強くて気づかないなど。手品などもこれにあたる。ピエゾ素子ではないが、同じ音でも振動を電気に変え数値化したら、その違いは明確になるだろうが、その違いをあえて自身の感性で探すのも面白いかもしれない。
無音と思っていたものが実は無音でなかったり、過去に、収録曲数が99曲あるのに、数曲目以降は無音だったという面白い試みの作品がいくつかあったが、それも今になって聴いてみたら何かが聴こえてくるかもしれない。レベッカの「MOON」という楽曲に「先輩」という謎の声が入っていたというのが昔、話題にもあったが、そうしたことも気づけるかも?
前述の『音楽の基礎』だが、これまで音を意識していたものを、あえて無音、休符へ意識をおくことでまた音楽の捉え方も変わってくるかもしれない。既成概念を一回取り払い、昔聴いた楽曲をもう一度聴いているみるのも一つだ。【木村陽仁】
- この記事の写真
ありません
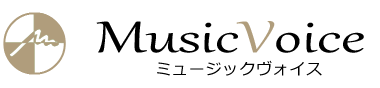
 “ハズレ音源”に導かれる音楽の幅
“ハズレ音源”に導かれる音楽の幅