今こそミクスチャーと言いたい
――ジャズとロック、それぞれのシーンはどう違ったのでしょうか?
松下マサナオ 難しいですね。正直僕らも厳密に分けているわけではないので。
別所和洋 ただ、やっぱり観に来ている人が違うというのはあります。(ジャズの方が)年齢層も高めだと思いますし。
中西道彦 あと座っているか、立っているかも。ジャズ箱だとジャズとそれに派生した音楽を聴きに来ているお客さんが多かったですね。
松下マサナオ それからライブに来るときの目的も結構違いますね。特に僕ら世代のジャズを聴く人は曲自体よりも、どうインプロヴィゼーション(即興演奏)するのかを聴きに来る人が多いんです。「あの曲のあのサビを聴きたい!」という感じではなかったんですよね。そこから、より「あの曲聴きたい」というシーンに入っていった感じです。
別所和洋 それによって、人の目に触れる機会が増えましたね。より色んな人と繋がって、どんどん広がっていきましたし。
松下マサナオ そうだね。「ライブハウスでライブをやる」という事がメインになった事によって、逆に僕らは先端のジャズミュージシャンと仲良くなる事ができたんです。向こうがこちらに「こういう音楽をやっても、ああいう場所でできるんだ」と興味を持ってくれて。
逆に、僕らも日本のジャズメンで尊敬している人が沢山いて、そういう方たちに今でも注目しているんです。なので、時間があればライブに行ったりしています。そういう時にジャズクラブで演奏する面白さにも気づいたんです。先日、ブルーノート東京でライブをしました。その際「ブルーノートが埃っぽかった(編注=格式高くなく気軽に楽しめた意)」とツイッターとかで書いてあって。いつも座って静かに聴く所で、ノリノリで聴くみたいな違う楽しみ方ができるんです。
今はブルーノートだからと言って、ジャズのスタンダードなライブだけじゃなくて、フュージョンとかロックとかポップス、演歌っぽい人もいます。そういう多様性のある所でライブをするのも僕らにとっては面白くて。だから反対に、いわゆる“ロックのライブハウス”でジャズメンが演奏する様になって、90年代のニューヨークみたいな自由な感じになれば楽しいかなと。繋げられるものは繋いで、あまり狭い感じの活動にならない様にしてます。
そのことは、こちらのシーンに来てわかった事なんです。ジャズのライブハウスだけで演奏していた時は、ロック箱に行くと「ただ音でかくて、細かい音が聴こえないな」と思ってました。でもPAをこちらで呼んで、音響を持ち込んで、という風にやれば、凄く良い音でライブができるんです。それをジャズクラブの大きい所でやっても、それはそれで成り立つし。結局手間を省いてやろうとしていたから、今まで上手くいかなかったのがわかりました。
――海外ではジャズメンが、ジャズ以外の音楽をやるという動向もあります。それに関してはどう思われますか?
中西道彦 僕は自分がジャズメンだった経験がほとんど無いので。外から見るとジャズメンって、例えばデヴィッド・ボウイの『★(ブラックスター)』(編注=2016年作。新世代ジャズミュージシャンたちが演奏を担当した)で演奏しているメンバーもジャズメンと言われているかもしれませんが、その括りじゃなくて「格好良い音楽をやってる人」としか思えないんです。それがジャズはジャズ、ロックはロックという風に分かれているという風な感触は持っていなくて。だから僕は違和感が無いんですよ。格好良い音楽をやっていれば。
松下マサナオ 「アカデミックな事をやっている人たち」という様な括りですよ、「ジャズメン」というのは。「今やっとジャズメンが」という風に言う人がいますけど、状況は昔も今も変わらないと思うんです。でも、今コンテンポラリーなジャズは売り時だと思うんですよ。そのタイミングでこのシーンをピックアップしようとしている人が出てきている。そこに僕らよりも下の世代が食い込んできて「あ、ジャズだな」という感じになってはいますけど、僕らはそこを意識している訳ではないです。
――つまり、ジャズとかロックとか、ヒップホップというジャンルは全く関係ないということですね?
松下マサナオ そうですね。今こそ「ミクスチャー」と言いたい(笑)。
斎藤拓郎 自分達が面白いと思えたり、楽しめる事というのを基本的に大事にしているんです。
海外勢に負けているとは認めない
――先ほど述べられた、「ジャパン」な感じにしないという事の意味は?
松下マサナオ これも難しいんですけど。ジャズじゃなくても、上澄みだけすくった物をさらに薄めて「元々これ何味だっけ?」という風にした方がわかりやすいんですよ。だから僕らもここまで来るのに7年かかったんです。アート全般に言えると思うんですけど、「濃い物」というのは、同じような事をやっていても伝わりづらい。それでも変えたくなかったんですよ。だから今でも変えていない。そこはメンバーが唯一、ルールにしている部分だと思うんです。
今、僕らってめちゃくちゃ媚びているんですよ。「もっと動こうぜ、演奏中」とか。自然に動いてはいるんですけど、もっとわかりやすい方が良いじゃないですか。そこは音と関係ないですけど、そういう所を押し出そうと思っているんです。ただ、基本的に変えたくないのは、海外のアーティストが見た時に「こいつら、すげえ良いじゃん」と単純に思えるものを提供する事で。
「常にリスナーに向けていない」というのは、僕らの良くない所でもあるんですけど、そこは絶対に変えないんです。自分達に向けて演奏する。自分達が満足できるものとか、自分達がワクワクするものを常に作ろうと思っていて。拓郎が作るメロディラインはポップでわかりやすいものになっているんですけど、よく聴くと「これ4人でやってるの?」という曲を作り続けています。
海外のアーティストは皆フィジカルも凄く強いし、手もでかい。日本人は音量とか、音の立ち上がりとか全てにおいて劣ってしまうんですよ。それを「日本人なんだから」と言って、言葉を変えてやるのが僕は凄く嫌なんです。できるだけ向こうのアーティストに対峙したい。僕が言う「海外」は基本的に米国の事です。米国の音楽が大好きなので。「ジャズは米国」、「ドラムは米国」と、いまだに思っていますから。「日本っぽくしない」というのはそういうことです。
――海外に対して劣等感はないですか?
別所和洋 もちろんありますよ。凄いピアニストとか見たら、全然手が動いてないのにとても速いパッセージを弾いていたりとかして。あれは確かに分析すると「手がでかいから」とか「日本人の骨格じゃできない」とかあると思います。それができないからといって、負けを認める訳じゃない。だから、やっぱり練習じゃないですか。
松下マサナオ あいつら(海外勢)、練習もしてるからね(笑)。
中西道彦 骨格とか筋肉の構造とか立ち方、体をどう使うか、というところまで掘り下げて研究した事もあるんです。最終的に収束していくのは、僕らが好きな奏者はそれを意識してやっているわけじゃないという事です。ただ、日本人として全く無い物に向き合う時に、僕らが出来る唯一の事は分析する事じゃないですか。
松下マサナオ 僕は音量がコンプレックスですね。海外の人に絶対勝てないですから。だから、そこはミニマムにした状態で、絞っているんです。そのままコンパクトにしたものをやろうと思っています。だから音量は捨てました。海外に行った時に、僕の太ももの太さが、彼らの腕の太さだったりしたので。それでも、やっている内容自体は常に負けない様にしています。
斎藤拓郎 先ほどもあった「日本っぽくしたくない」とは言いつつも、(海外を)真似しているわけですからね。オリジナルには絶対勝てないと思うんですよ。じゃあ、どうやって戦うか、それは自分の持っているものを出すしかないので。結局は「日本人ぽさ」を織り交ぜていく、という事を考えています。どう混ぜれば、格好良く聴こえるかみたいな。
とは言ってもそんなに深く考えずに、感覚的に曲を作るんです。日本人から自然に出てくるものが「日本人ぽい」と僕は思うんです。自然に出てきたものをまず作って、そこに影響を受けた音楽のエッセンスを混ぜていく、という風にやっていくと良い感じのものが作れるんじゃないかなと。メロディとか、僕の作るものは本当に日本人ぽいものだと思います。
松下マサナオ そこが良いバランスになっているよね。
別所和洋 薄めるんじゃなくて、混ぜてそのまま出すみたいな感じですね。その混ざり具合もしっかり吟味して。
松下マサナオ 拓郎のやっている事はYMO(Yellow Magic Orchestra=坂本龍一、高橋幸宏、細野晴臣によるテクノバンド)感があるんです。こっちで作ったものを、向こうにそのまま持っていくと、面白いと思われる要素というか。ジャズ色が強いのは、やはり別所ですね。ハーモニーとかもそうだし、曲の構成もジャズの影響がある。それをコーティングした拓郎の日本人的な部分。そしてそのコアとして、僕らが米国で学んできた、ビートやリズム感というのが、Yasei Collectiveの音楽になっていると思います。


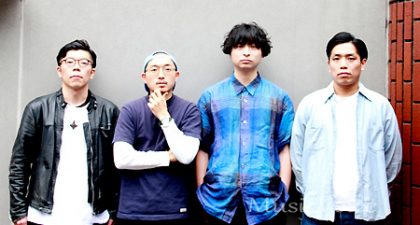


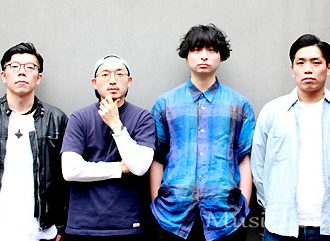




 Yasei Collective「好きなことやる」NCISとともに可能性見せた新体制ライブ
Yasei Collective「好きなことやる」NCISとともに可能性見せた新体制ライブ Yasei Collective「別所がいてYaseiがありました」4人最後のステージ
Yasei Collective「別所がいてYaseiがありました」4人最後のステージ Yasei Collective、別所和洋が脱退「話し合った結果」
Yasei Collective、別所和洋が脱退「話し合った結果」 日本でやれば破綻してた、Yasei Collective ライブ感捨てた新作
日本でやれば破綻してた、Yasei Collective ライブ感捨てた新作 Yasei Collective、スペアザとの競演で魅せたスペシャルな一夜
Yasei Collective、スペアザとの競演で魅せたスペシャルな一夜  Yasei Collective、16台のカメラで超絶テク細部まで 新曲MV公開
Yasei Collective、16台のカメラで超絶テク細部まで 新曲MV公開