DOBERMAN INFINITY「インフィニティの歴史において必要な作品」音楽ライター・渡辺志保氏によるオフィシャルインタビュー公開

DOBERMAN INFINITYと渡辺志保
DORBERMAN INFINITYが放つ新作EP『milestone』(6月23日配信リリース)は、全編をBACHLOGICがプロデュースを手がけた渾身の一作。DORBERMAN INFINITYの前身であるDORBERMAN INC.時代から彼らの音楽に親しんでいるリスナーは、この再タッグがどんな意味を持つのか、ありありと感じ取ることができるはずだ。
DORBERMAN INC.の屋台骨的存在でもあったプロデューサーのBACHLOGICは、今やAKLOやZORN、SALUといった名だたるラッパーたちを手がける国内トップレベルの至高のプロデューサーとなった。
『milestone』を聴くと、サウンド感もまるでかつてのDORBERMAN INC.が輝きを放っていた2000年代前半のような煌びやかさとヘヴィさを纏っていることに気が付く。そのビートに乗るGS、P-CHO、KUBO-Cらのラップも、デビューから20年以上を数える今だからこそのリアルな気持ちや葛藤を歌ったものに。そこに、BACHLOGICのビートを再解釈したKAZUKIのコーラス、そして華を添えるようにエッジーなフロウで聴かせるSWAYのラップが加わり、個性あふれる全6曲が完成した。
荒削りだった魅力を取り戻すようでいて、DORBERMAN INFINITYとしての未来を見据えるような、今後に向けての道標となる稀有なEP。まずは分厚いドラム・ビートの鳴りに身を委ねてほしい。
―今回のEP『milestone』は、全6曲ともBACHLOGICのプロデュース楽曲です。なぜ、今のタイミングでこうしたEPをリリースすることになったのでしょうか?
P-CHO:以前、スタッフさん含めたメンバー会議で、自分たちが次のステップに行くために何をすべきか、ということを話し合っていたんです。その時に「もう一度、原点回帰的なものをやってもいいんじゃないか」というアイディアが出て、SWAYから「BACHLOGICさんとやるのどうですか?」と。それがコロナ禍の前の話だったんですよね。
―BACHLOGICといえば、DORBERMAN INC.時代を支えた盟友とも言える存在であり、今や日本のヒップホップ・シーンをも支える名プロデューサーでもあります。最初はどのようにアプローチをして制作が始まったのでしょうか。
P-CHO:最初、自分がBACHLOGICに連絡させてもらって。そうしたら、「じゃあ、やろうか」と返してくれたんです。その後に「ビートのストックを一式送るわ」ってバーンと送ってもらったんですよ。
KAZUKI:懐かしい。みんなでスタジオで聴きましたよね。
P-CHO:でも、そのすぐ後にコロナ禍になってしまって、BACHLOGICとの制作は保留みたい形になってしまった。BACHLOGICも「焦らんでいいやん」長い目で見てくれていたので、まずはコロナ禍を乗り越えた時間を表現した作品、ということでアルバム『LOST+FOUND』を大切にしつつ、『LOST〜』を作り終えてから、改めて取り掛かったんです。
ー「Where we go」のリリックには、"スイッチ入れたオーディオ / INC時代を爆音で〜真夜中あの人にビートをオーダー"という描写があります。実際に、そんな感じで連絡を取った?
P-CHO:リリックの「INC時代を爆音で」という箇所に繋がるんですけど、やっぱり20年以上音楽をやっていて、そのライブラリの中にBACHLOGICと作った音楽が残っているということは、自分のキャリアの中でもすごく大きいことなんです。あのときの音楽は今でも聴き返しますし、やっぱりBACHLOGICと作る音楽っていいな、と感じる。なので、最初にBACHLOGICには自分の思いをそのまま伝えました。「真夜中」と言っても正確には11時半くらいだったんですけど(笑)。
―INC.時代から時間とキャリアを経て、2023年にDOBERMAN INFINITYのメンバーとしてBACHLOGICさんとともに曲を作るということに関して、感慨深さはありましたか?
KUBO-C:結構前から、「一緒にまたやりたいな」っていう気持ちはあったんです。『LOST〜』もリリースして、これでちゃんとBACHLOGICとの制作に取り組めるぞって時は、みんなもそうだし、僕もテンションが上がって。EPが形になって完成していくにつれてすごく嬉しくて。自分たちで一回、曲を完成させたものをBACHLOGICに送ると、BACHLOGICがさらに完成形にして返してくれるんですよ。その仕上がり具合はヤバかったですね。P-CHOから連絡が来て、飲みに行かされたくらい(笑)。INC.のときのあの感じを、INFINITYでもう一度出来るってことがすごいな、と。それこそ感慨深いですよね。。
GS:BACHLOGICは、自分たちが音楽を始めたときに一緒に走り出した人ですし、当時、DORBERMAN INC.が駆け上がっていけたのは彼の大きな力があったからこそ、ということは声を大にして言いたい部分でもある。でも、だからこそ自分の中にハードルが出来てしまっていたんです。あの頃INC.としてラップしていたような新鮮さやセンセーショナルさを今の自分が出せるか?って。でも、実際に制作してからは自分が思っていたプレッシャーとかは全くなかったですね。INC.時代の気持ちそのまま、というよりも、SWAYやKAZUKIも一緒に、INFINIATYのメンバーとして共に制作できたのはよかったです。改めて自分のヒップホップ熱というか、そういう初心に戻ることができた作品になったなと思います。
―逆に、INC時代のメンバーとは世代も異なるKAZUKIさんはどんな思いで制作に臨んでいましたか?
KAZUKI:BACHLOGICさんに対してはスパルタなイメージがあったので、気合いを入れて挑みました。制作中、「どうやって(メロディを)ハメていこうかな?」と悩んだ曲もあったんですけど、自分が思うままにレコーディングさせてもらって。その後、BACHLOGICさんが楽曲を”料理”してくれるんですけど、KUBO-Cさんが言う通り、返ってきたものが本当にすごくて。「こういうことなんや!」て肌で実感できました。声の処理とかも、すごいアレンジになって返ってくるんです。
SWAY:めちゃめちゃな米をBACHLOGICさんに渡しても、すごく完璧なチャーハンになって戻ってくる、みたいな(笑)。
P-CHO:そうそう、絶妙な抜き差し加減でね。
KAZUKI:素材さえあれば、しっかり料理してくださるんだなってことが分かりましたね。
―改めて『milestone』を完成させて、また、久しぶりにBACHLOGICとの制作を経たことで得た気づきなどはありますか?
GS:INC.時代は、今とは違う観点で音楽を作っていたんです。「自分たちはこうだ」とか、「これがおもろいやろ?」っていう主張のみでしか音楽を作っていなかった。対して、INFINITYになってからは「これを受け取った人がどう思うんだろう」というところまでを考えて音楽を作るようになった。これって、自分の中では大きな違いなんですよね。こうした変化は成長や進化という言葉に置き換えられるのかもしれないですけど、どちらとも音楽を作るということには変わりがない。だからこそ、どっちかしかやらないっていう考え方はナンセンスだなって改めて感じさせてもらいました。自分たち自身で音楽を楽しむことが原点にならないといけないのに、いつしか誰かのための音楽にしていたのかな、と。この『milestone』は、インフィニティの歴史において必要な作品だったんじゃないかな。
―昨年は『LOST+FOUND』のリリースに伴う大規模なツアーあり、先日はファンクラブ限定のライブハウスツアーを終えたばかり。コロナ禍以降、ファンの方とコミュニケーションを図る機会も増えたと思うのですが、リフレッシュした気持ちなどはありますか?
SWAY:色々と大変ではありましたけど、改めてあの時間があったからこそ、気づかせてもらえるものもたくさんあったんだと感じています。こうやって、ようやく前の状態に戻りつつあるからこそ言えることだと思うんですけどね。これからまたまたツアーが始まるんですけど、声出しできるっていうことが、すごく楽しみなんですよ。
KAZUKI:僕らも遠い距離感に慣れてしまっていたところもあったので、改めて、久しぶりのライブハウスの距離感とか、MCの時にリアクションが返ってくるとか、そうしたやり取りがすごく楽しかったですね。ソロ・アルバムのリリースイベントでもすごい近い距離でコミュニケーション取れましたし。本当に当たり前のことですけど、その当たり前なことがしばらくやれてなかったんで、幸せを感じました。この新鮮さとかありがたみを忘れずにいきたいですね。
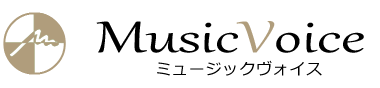




 THE RAMPAGEやFANTASTICS、LDH所属アーティスト総勢106人が大集結 圧巻パフォで2023年を締めくくる
THE RAMPAGEやFANTASTICS、LDH所属アーティスト総勢106人が大集結 圧巻パフォで2023年を締めくくる DOBERMAN INFINITY「こんな時代に負けんなよ!」ツアーセミファイナル東京公演レポート
DOBERMAN INFINITY「こんな時代に負けんなよ!」ツアーセミファイナル東京公演レポート DOBERMAN INFINITY、ニューアルバムを引っ提げた全国ツアー開催決定
DOBERMAN INFINITY、ニューアルバムを引っ提げた全国ツアー開催決定 DOBERMAN INFINITY、ニューアルバム詳細公開&新曲10曲のMV制作決定
DOBERMAN INFINITY、ニューアルバム詳細公開&新曲10曲のMV制作決定 SWAY「もう一回攻めていこう」3年半ぶりのソロアルバムで見せた気概
SWAY「もう一回攻めていこう」3年半ぶりのソロアルバムで見せた気概 DOBERMAN INFINITY、女優石川恋が出演する新曲「夏化粧」MV公開
DOBERMAN INFINITY、女優石川恋が出演する新曲「夏化粧」MV公開 DOBERMAN INFINITY「夏化粧」が「めざまし8」8月度EDテーマソングに決定
DOBERMAN INFINITY「夏化粧」が「めざまし8」8月度EDテーマソングに決定 DOBERMAN INFINITY「Updating Life」先行配信がスタート
DOBERMAN INFINITY「Updating Life」先行配信がスタート