『ラ』というタイトルを、最初にフラットな状態で人々が見たときに、どんな風に思うのか
――今回の撮影は、埼玉・川越のほうでおこなわれたのでしょうか?
高橋朋広 そうですね、一都六県くらいを股にかけて、東京、千葉、高崎とかいろんなところでやりましたが、舞台は川越ですね。川越の雰囲気が良いと思ったんです。駅前は雑多な都会の雰囲気を装っているけど、ちょっと離れたらもう“え? ここって電波入る?…”みたいな。幅があるところがいいと思いました。自分の地元がそういう雰囲気だったので、自分の原風景みたいなところに寄せた部分はあるかもしれません。
――特徴的な場所ですよね。この物語の着想についておうかがいしたいのですが、どのようなところからこのストーリーの核を考えついたのでしょうか?
高橋朋広 赤ちゃんの産声が「ラ」の音だと知ったことが企画のきっかけです。「ラ」が始まりの音だとしたら、すごく辛いところから何かを始めようとする人、一歩踏み出そうとする人を描きたいと思いました。元々、“誰かが人生を駆け抜ける瞬間”を描きたいと思っていたんです。自分が映画でやりたいことの一つは、その人物の長い人生の中で最も人に見せる価値のある瞬間を切り取ることなんです。だからこそお客さんに見てもらう価値があるし、見てもらって価値があるって思ってもらえる。
あとはそのテーマに対して、いろんな作劇上の要素を組み合わせていきました。物語上の動きや展開というのはあくまで手段であって、本質的に見せたいものは人間の弱さであり、そこからまた始めようとする強さ。
テーマと描いていくストーリーっていうのは、付かず離れずの関係というか。テーマばっかりごり押ししたって、それってエンタメというか人に見せるものにならないと思っています。
――それは、興味を引かないですよね。
高橋朋広 昔から強く思っているのは、人混み、例えば渋谷のスクランブル交差点なんかで、自分で思ったことを叫んだとして、別に誰も耳を傾けないですよね。じゃあ立ち止まってもらうにはどうするか?映画とか、音楽とか、そういう芸術であったりエンタメを纏うことで、初めて人は耳を傾けると思っています。もちろんエンタメ、つまり人を楽しませることも、それそのものが目的だったりもするんですけど。だから、自分の中でそれらは両輪と思って作っています。
――なるほど。それにしてもこの『ラ』というタイトルの発想がすごいですよね。一文字でタイトルなんて。桜田さんは、この“ラ”という音に、自分の中で響くところはありますか?
桜田通 この『ラ』というのは、ギターとかでいえば“A”の音とか、そういうところの印象はあるかなと。“始まりの音だ”という意味では、例えばメジャーな映画だったら『始まりの音』というタイトルでもいいくらいだと思うけど(笑)、それをあえて『ラ』という、やや玄人向けのタイトルにしたというところには、こだわりも感じますね。
慎平を演じ終えた今でもこの映画が『ラ』である意味をすごく理解できている。『ラ』というタイトルを、人々が最初にフラットな状態で見たときにどんな風に思うのかはわからないけど…できればやっぱり映画を見てもらい、タイトルにも納得してもらえたら良いですよね。
――撮影の仕方としてというかすごく長回しのシーンに強い印象を感じました。そういった部分に、高橋監督は何か意図されたところもあったのでしょうか?
高橋朋広 もちろん事前にある程度のイメージというか、大枠はロケハンの段階や台本の段階で決めてはいました。ただ、事前のリハーサルで彼らの生身の芝居を見たときに、本物の映画にしたいなという気持ちが芽生えたんです。
例えば電話をするシーンでは、基本は常に相手にいてもらい、リアルに電話で会話をしてもらったりしました。普通は、電話のシーンは事前に相手側の通話を録音して、撮影ではそれをスピーカーから流してやるんですけど、そのやり方だと台本に制限されてしまうし、やっぱり台本以上のことってなかなか出てこなかったりするんです。
――リアリティの追求という部分ですね。どのようにそれをキャストやスタッフに伝えたのでしょう?
高橋朋広 一貫してお願いしていたのは“台本を気にしなくていいよ”ということですね。台本というのは、あくまでガイドライン、“この方向に向かっていこう”というものなので、それが原因で縛られてしまうのは良くない。今回はそういった趣旨をちゃんと理解してくれている役者さんばかりだったので、台本は良い意味で無視してくれることが多かったです。そうやって有機的に変えていけることが、監督と脚本を同じ人間が担当するメリットかなと思います。
相手が言ったことに対して、リアクションしていくのが芝居だと思っていて。そうやって芝居をすれば自然と台本には無い吐息とか、台詞にもつかない何かが出てきたりする。それがスクリーン上のリアルを形成すると思っています。一連の長回しでいったからこそ出る本物の空気感みたいなものがあるので、5分10分の芝居を、何回もやってもらいました。もちろん、カットを割るほうが効果的だと思えばそうしましたけど。
――結構何回もやられたのですか?
高橋朋広 そうですね。芝居はキャッチボールなので一言目が変わればゴールも全然変わってきます。例えばシーン途中のニュアンスが伝えたいものと違っていたとして、その部分だけ撮り直してもそれはリアルにはならない。だから途中の部分だけ撮りたくても、毎回頭からやってもらいました。
――それは桜田さん、笠松さん、福田さんそれぞれに対して“いけるぞ”という予測のもとで、ということだったのでしょうか? あるいは完全にどんなものが出るのか楽しみだな、と不確定要素に賭けたような感じでもあるのか…。
高橋朋広 もちろんどちらもあります。ただ今回、撮影に入る前にリハーサルをやってもらったんですが、そこでは台本の部分をリハーサルするというよりは台本にないところ、例えば二人がどういう風に出会い、どういう風にこれまでを過ごしてきて、映画『ラ』の中で描いてる部分にたどり着いているのか、そんな歴史を埋める作業みたいなものをみんなでやらせてもらったんです。
台本に出ている部分というのは、あくまでその瞬間を切り取られているにすぎない。でも実はその前にいろんな文脈があるからそういう風になっている、という解釈をみんなで共有しました。その中でリアルな掛け合いの芝居というか、本当に当事者二人がそこで話しているような臨場感みたいなものを作りたかったんです。
――リハーサルの時点では、桜田さんとかも、これ現場はどうなるんだろう? すごく楽しみみたいな感じだったのでしょうか? それともこりゃ辛いな、という感じか…。
桜田通 いや、そんなことすらも、何も考えないでくらいに慎平のことでいっぱいでした。リハーサルの場所はロケ地ではなくただの貸しスタジオで、小道具も限られたものしかなくて、本当に創造力を使いましたし。でもなるべく今まで僕が「桜田通として生きてきた26年間」を、「慎平として生きてきた20数年間」に変えていくくらいの深みが欲しかったので、リハーサルの間は、そこでできるだけ慎平としていようと、何回も生きる時間を繰り返していった感じでした。
その数が一回でも多ければ多いほど、慎平としての歴史が僕の中に一個増えていく。そしてなるべく慎平としての時間をいっぱい過ごして、最後に現場で慎平としてその瞬間を切り取ってもらう。そんな感覚で撮影に臨んだので、普段の撮影のように「この作品に出るから、この台本を覚えて現場に行く」みたいなことから比較すると、ちょっと捉え方が変わっていました。


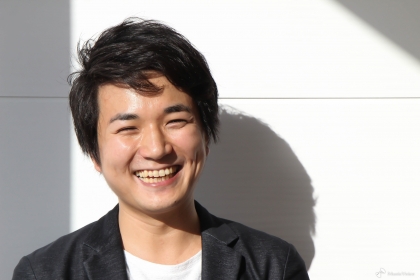






 神木隆之介×松山ケンイチ×桜田通、クセが強い「節約川柳」表彰式
神木隆之介×松山ケンイチ×桜田通、クセが強い「節約川柳」表彰式 桜田通、ローマを旅する 壮大なイタリア文明宮に「すごく圧倒されました」
桜田通、ローマを旅する 壮大なイタリア文明宮に「すごく圧倒されました」 山崎賢人、土屋太鳳にフラれる「ごめん、賢人くん」「うん」
山崎賢人、土屋太鳳にフラれる「ごめん、賢人くん」「うん」 大政絢、中村アン、堀田茜、森星、山田優、泉里香、西内まりや、桜田通、吉野北人が美の競演
大政絢、中村アン、堀田茜、森星、山田優、泉里香、西内まりや、桜田通、吉野北人が美の競演 桜田通にあわせ山崎賢人&土屋太鳳&三吉彩花&朝比奈彩がギャルピース!
桜田通にあわせ山崎賢人&土屋太鳳&三吉彩花&朝比奈彩がギャルピース! 桜田通が指摘、ロイの耳にたくさんの糸くず
桜田通が指摘、ロイの耳にたくさんの糸くず 桜田通、古着リメイクに興味津々
桜田通、古着リメイクに興味津々 みちょぱ、幼少期以来の裁縫に挑戦 桜田通はあるリメイクが気になり…
みちょぱ、幼少期以来の裁縫に挑戦 桜田通はあるリメイクが気になり… みちょぱ、ロイのハイテンションに「ちょっと抑えめで」
みちょぱ、ロイのハイテンションに「ちょっと抑えめで」