都はるみ「歌屋」と名乗る理由、アンコ椿、伊豆大島に秘めた思い

伊豆大島での野外コンサートのもよう(C)産経新聞社(サンミュージック提供写真)
デビュー55周年を迎えた歌手の都はるみ。2015年来、事実上の音楽活動休止状態にあるが、17年にラジオ出演した際には「良い歌詞に出会えば良いけど、なかなか巡り合えない」とその活動に含みを持たせた。一般的には「演歌歌手」という印象はあるものの、自身を「歌屋」と例えるなどその音楽性は型にはまらない。なぜ「歌屋」なのか。そこにはジャンルにとらわれずに歌いたいという思いがある。それは彼女のコンサートにも表れている。=写真=伊豆大島での野外コンサートのもよう(C)産経新聞社(サンミュージック提供写真)
自然とともに生きる人に寄り添う演歌
怒号にも似た風の音、波が波を打ち消す音、椿の花びらから滴る水の音、人のすすり泣く声――、そうした情景を、言葉、そして歌唱法をもって表現しているのが演歌ではないか。
民謡の流れを汲む演歌は、郷土との関わりが強い。それは、歌詞に使われる言葉からもうかがえる。例えば「海峡」や「白波」、あるいはその土地の名称。若い世代には少し遠い存在になってしまったが、改めて真剣に向き合うと、演歌は、自然と共にあるのではないかということに気が付く。自然とともに生きる人の営み。それを歌詞やメロディ、そして歌唱法をもって表現している。
美空ひばりの後継者ともうたわれた都はるみ。「はるみ節」と呼ばれる、うなり声のような力強いこぶし回しや、波打つような深いビブラートが特長で、それらを駆使した圧倒的な歌唱力で人々を感動させている。その特長こそが自然界そのものと言える。風林火山ではないが、こぶしは時に雷鳴のごとく、深いビブラートは荒波のごとし、表情豊かな歌声は雲海を帯びた峰のように。都はるみから発せられる歌はそうした自然界の脈動を感じさせる。
しかし、都はるみのコンサートをみると、演歌だけではない様々な音楽性がうかがえる。圧倒的な歌唱力をもって表現するのは“演歌”という枠組みを超えたものと言える。それこそ自身を例える「歌屋」の真意が見え隠れする。
伊豆大島を描いたアンコ椿
その一端は、今年2月に発売された、“都はるみ伝説の野外コンサートの映像3作品にも表れている。そのうちの一つのコンサートを引き合いに、都はるみの歌と向き合ってみたい。
伊豆大島波浮港開港200周年記念として2000年7月26日に、東京・伊豆大島のトウシキ広場でおこなわれた野外コンサート。この地での単独コンサートは約20年ぶりだった。都はるみはこの地との関わりが深い。都はるみの代表曲に「アンコ椿は恋の花」がある。実はこの曲は都はるみにとって3枚目のシングル。期待の新人としてデビューした都はるみだったが、そのデビューシングルは思いのほか振るわなかった。そして3枚目、その後彼女の歌の半数以上を手掛けるようになる市川昭介とタッグを組み作詞家星野哲郎がこの地を舞台に詞を書いたのが「アンコ椿――」だった。この曲の大ヒットで都はるみの名前と伊豆大島は全国に知れ渡った。第二の故郷と言うのはこのためだ。そんな都はるみが20世紀の終わりにコンサートの地に選んだのがここ伊豆大島。
この年、三宅島では火山性地震が頻発し、神津島では震度6弱、新島では震度5弱などを観測。不安が募るなか、町民の想いに押されるように来島した都はるみは歌をもって元気にした。大島町によればこの時の観客動員数は4500人。当時の島民人口が9224人(総務省統計局・国勢調査)だから、その半分が訪れたことになる。なお、コンサートの入場料は無料、会場内にチャリティーボックスを設置し、その収益はこの地震の被災者に寄附された。
コンサートを触れる前に「アンコ椿――」についてもう少し触れたい。この曲は、力強いうなりで<アンコ~♪>と歌いあげる姿が印象的だ。歌の舞台は伊豆大島で、歌詞には島や人々の様子が描かれている。この「アンコ」は、伊豆大島の言葉で、目上の女性に対する敬称「姉っこ」がなまったものと言われている。また、「椿」は同地域を代表する植物だ。1965年には同名で映画化され、淡い恋物語として描かれた。叶わぬ恋心、または遠くの人あるいは故郷を想う心がうかがえる。言葉にできない心から触れ出す愛しさが、前述の<アンコ~♪>から滲み出ている。その後に続く歌詞はこうである。<アンコ椿は アンコ椿は ああ すすり泣き>。筆者には何とも切なく響いた。
都はるみは、それを<アンコ>と力強いこぶしで表現し、<椿は>は糸のように細く伸びやかに歌い上げている。もしかしたら男の心情をもああいう力強いこぶしで表現しているのかもしれない。また、「恋物語」を描きつつも、三原山大噴火などの大震災があるたびに故郷を離れなくてはならない、島民の辛い思いも投影されているように感じる。それは伊豆大島に限ったことではなく、今も避難生活を送らなければならない東日本大震災などにも重なる。
和洋折衷、まさに奇想天外なコンサート
その歌の舞台ともなった伊豆大島でのコンサート。都はるみの想いは容易に想像できるだろう。コンサート前日には、波浮港見晴らし台に歌碑が建てられた。その式典に出席した様子がDVDに収められている。その歌碑は、同島および波浮港を広く全国に知らしめた功績だが、伝えたのは地名だけでなく、その土地と営みを共にする人々の姿と郷土愛だ。ちなみに、島に向かう連絡船内の操舵室で船長と談話している姿に、好奇心旺盛な一面を見た。
そして本番。“晴れ女”を象徴するように、時折降っていた雨は開演前にはぴたりと止んだ。野外コンサート会場。露わになった骨組みの合間からは夕日に染まる雲が広がる。神々しい。会場にアカペラの「波浮の港」の歌声が流された。続いてステージに登場した都はるみは大地に溶け込むように緑を基調とした着物姿で歌い上げていく。歌は「しあわせ岬」。自身の想いも表すかのように。
<しあわせになりたいなァ>
<愛する人の胸に抱かれて>
(中略)
<あゝ そうよここがあなたの故郷>
<帰る時をわたし わたし待ちます>
伸びやかな美しい歌声で人々の思いを紡いでいく。「しあわせ岬」は通常コンサートの1曲目に持ってくることはないという。それだけ特別な思いがあった。そして最初のMCではこう語りかけた。「(震災を受けた)新島・神津島・三宅島の皆さんは今大変です。地震とか雨とかをきょうは吹っ飛ばすつもりでやりますので、最後までお付き合い下さい」。
当時の持ち歌は約200曲。その半分以上を市川昭介(1933年―2006年)が作曲した。都はるみは市川が手掛けた歌のなかから「自分に合っているのではないか」という曲を選び、メドレーを披露した。そのメドレーはまさにユニークで、ロックのシャウトのようなこぶしから始まった「惚れちゃったんだョ」から「馬鹿っちょ出船」、「はるみの三度笠」など、歪んだエレキギターサウンドと和楽器が織りなす和洋折衷のサウンドのなかで、生き生きと歌い上げた。都はるみ自身も腰をくねらせ陽気に踊り、メドレーをジャンプして締める。
そして市川が登壇。当時の思い出話の後に市川の指揮で「アンコ椿は恋の花」。続いて市川の作品で大ヒットした「大阪しぐれ」「涙の連絡船」を市川の指揮で歌う。力強いうねりが特徴の「アンコ椿は恋の花」に対して、いつ会えるかわからぬ男を待つ女性の心情を表現する「涙の連絡船」のこぶし回しは繊細な糸のよう。
<今夜も 汽笛が 汽笛が 汽笛が・・・・>
<独りぽっちで泣いている>
<忘れられない 私がばかね?>
<連絡船の 着く港>
その世界観に思わず市川も「良い歌、うたっているね」と笑顔を見せた。ミリオンセラーを記録してNHK紅白歌合戦出場への期待が高まった「アンコ椿――」。しかし、その力強いうなりが当時評価されずに出場には至らなかった。それならば、ということでそれを極力抑えたのが「涙の連絡船」だった。都はるみ、そして市川にとっても想い入れが強い曲だ。
一方、情緒に浸ったかと思えば、尺八、お琴、篳篥(ひちりき)、そして、エレキギターやシンセサイザー、ドラムが入りこむ雅楽とロックを融合した、インストゥルメンタル「戦争と平和」も届ける。まったくもって奇想天外な展開だ。
その後、松明が灯るなかで「大原絶唱」を熱唱。そしてコンサートは後半、目を見張るのは「北の宿から」と「おんなの海峡」「王将一代 小春しぐれ」。なかでも「王将一代 小春しぐれ」は通常のコンサートでは披露されない希少曲。三味線を伴奏にして独特の節で語る、いわゆる浪曲を、歌謡曲に組み込んだ。その歌の合間に“歌われる”浪曲、そして語りはまさに圧巻。歌ではなく語りでその世界観を表現する。その二節にある<小春…わい、今から命がけや!>は叫びにも似た気迫みなぎる語りで、まさに息を飲む場面だ。
そして最後は都はるみのテーマ曲とも言える「好きになった人」。観客は手拍子、その顔は笑顔に溢れている。ステージ中を右へ左へステップを踏んで元気に飛び跳ねる姿は変幻自在で型にはまらない。しかし、その行動の背景には、人々に寄り添い、日々の悲しみ辛さから解放され明日に向かって明るく楽しく元気になってもらいたいという一心があるのではないか。歌だけでなく、時に笑顔で、時に驚きをもって見せる。
さて冒頭で都はるみは「歌詞に巡り合えない」と語った。量産される言葉でなく、人々に寄り添う言葉を求めているような気がする。そして「歌屋」という例え。演歌という枠組みが生まれる以前、歌謡曲はその時代の流行や文化に敏感でそうした音楽やトレンドを取り込んで様々なタイプの曲が歌われてきた。演歌というジャンルが登場した以降も、その枠にとどまることなく様々な歌を届けていきたいという思いが、その「歌屋」という名に表れている。音楽はその時代を映し出す鏡だ。都はるみは1990年代、演歌という枠に捕らわれずに行きたいという思いが強くなった。その思いの一端が今回のコンサートにも表れている。歌を中心に総合エンターテインメントとして様々な情景、元気を届けていくという覚悟。しかしそれは確固たる歌唱力があって成り立つもので、「歌屋」と名乗れるのは限られた人だ。都はるみを通してその歴史、そして本質に触れる。いま見つめなおす時が訪れている。
ちなみに、1994年の『平安建都1200年記念 都はるみ 大文字送り火コンサート こよひ逢ふ人みなうつくしき 晶子』や、93年の『都はるみコンサート ねぷた伝説』はまた異なる一面も見せている。ジャズやブルース、ムード歌謡もあり、その多彩性がうかがえる。そのレビューは後日にする。【木村陽仁】
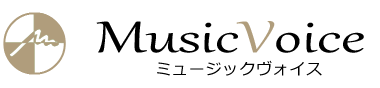



 自衛隊1日入隊やプロレス参戦…演歌歌手・上杉香緒里、体を張る理由
自衛隊1日入隊やプロレス参戦…演歌歌手・上杉香緒里、体を張る理由 北島兄弟、浅草神社でヒット祈願 “師匠”北島三郎に「恩返ししたい」
北島兄弟、浅草神社でヒット祈願 “師匠”北島三郎に「恩返ししたい」 ヴィジュアル系演歌歌手・最上川司「思い出深い味」地元・山形の肉そば再現
ヴィジュアル系演歌歌手・最上川司「思い出深い味」地元・山形の肉そば再現 改めて演歌の魅力に触れる、短いセンテンスで描写克明に
改めて演歌の魅力に触れる、短いセンテンスで描写克明に 増田惠子、13年ぶりシングルで阿久悠さん未発表詞を歌う
増田惠子、13年ぶりシングルで阿久悠さん未発表詞を歌う 岩佐美咲のステージで感じた歌唱力の高さ、演歌歌手の底力を実感
岩佐美咲のステージで感じた歌唱力の高さ、演歌歌手の底力を実感 岩佐美咲、芸能生活10年「本当に実感がない」全国行脚へ意欲も
岩佐美咲、芸能生活10年「本当に実感がない」全国行脚へ意欲も 丘みどり、初出場の紅白大舞台もしっかりと涙見せず歌い上げる
丘みどり、初出場の紅白大舞台もしっかりと涙見せず歌い上げる 三山ひろし、けん玉ギネス更新ならずもガッツポーズで決める
三山ひろし、けん玉ギネス更新ならずもガッツポーズで決める