PERSONZ、“39周年”を締め括るロック・パーティー開催 千秋がゲスト出演し「DEAR FRIENDS」をコラボ

PERSONZ&千秋
2024年に結成40周年を迎えるPERSONZが、“39周年”(サンキューイヤー)を締め括るライブ『I AM THE BEST TOUR 2023「Year-End Ultimate Rock Party」』をさる2023年12月30日に開催した。
2020年にミニアルバム『I AM THE BEST』の発表に伴い企画されていたものの、新型コロナウイルス感染拡大の影響により無念の中止となっていた『I AM THE BEST TOUR』。2023年5月から8月にかけて全国11都市にて全12公演が3年越しに開催され、文字通りPERSONZの“BEST”な楽曲をリストアップするツアーとして好評を博した。今回はその“Ultimate”=“最後の”、“究極の”というタイトルの通り、ツアーのエッセンスを凝縮しながらパーティー感溢れる特殊な演目を盛り込むという2023年最後のライブに相応しい祝宴だ。
会場は日本屈指のオフィス街の一角にある大手町三井ホール。ステージは全方位から客席に囲まれる、舞台・演劇用語で言うところの“出臍”(でべそ)という形。本来のステージから伸びた花道の先端にある張り出し舞台で今宵限りのショーが始まるとおぼしい(余談だが、この花道を有する舞台を見るとすぐに『ロックンロールオリンピック』を連想してしまうのはやはり世代だろうか)。
第1部はスペシャル・ゲストを招きつつ繰り広げられた珠玉のアコースティック・セット
開演17時の3分押しで、三味線JILL屋と渡邉貢がオープニングアクトとして登壇。今回の三味線JILL屋は、JILL、ななえ(七重)、いぶ(伊吹清寿)という従来の編成に加え、篠笛の玉置ひかりも参加。ご承知の通り、三味線JILL屋とはななえといぶが奏でる抒情的かつアグレッシブな三味線の旋律の中で、JILLが唄うPERSONZの名曲やロックにアレンジされた端唄を楽しませる和楽団だ。
「こんばんは。今日はお客様の見え方が全然違いますね。後ろの夜景を見てください」と、JILLがわれわれの視線をステージ背後へ注がせる。曠然たるガラス壁の向こうに広がる黄昏の都市景観。角度によっては東京タワーの見える客席もあっただろう。都会の喧騒が夕闇に溶けつつあるアーバンな雰囲気の中で最初に奏でられたのは、「TRUE LOVE」(1991年)。三味線2本と篠笛、四絃琴(ベース)の生音にシーケンスの旋律が加わり、天井高7メートルという開放的なホールの中でJILLの声が伸びやかに艶やかに響き渡る。三味線JILL屋が奏でる花鳥風月を慈しむ雅な世界が、都会の無機質な空間に温かい彩りを与えているようだ。「笛の音を聴くと春めいた感じ、小春日和を感じますね」とJILLが語るように一足早い春の訪れを感じさせた後、「次は手拍子をお願いします」と「びいはっぴい音頭」が披露される。あの「BE HAPPY」(1988年)を大胆にも音頭にアレンジ、春から一転、夏の盆踊りを思わせる一曲だ。時折、演者の後ろ姿しか見えない後方の観客に向けて唄いかけるなど、JILLは気遣いも忘れない。最後に「2017年夏に浅草のお座敷で初舞台を踏んでから早6年、三味線JILL屋はこれからもっとライブをやっていきたいです」とJILLが意気込みを語り、お囃子衆の3人に拍手を捧げながら送り出した。
気づけばステージ背後の陽はすっかり暮れている。JILLと渡邉はそのまま残り、藤田勉と本田毅が花道を渡って現れる。万雷の拍手喝采。ステージ上の4人の間隔も、ステージと客席の距離感も思いのほか近く感じる。本田がエレアコ仕様、藤田がハンドソニック(藤田いわく“音の出るサイドテーブル”。デジタル・ハンド・パーカッションのこと)を携えていることから、ここからアコースティック・セクションが始まるのが分かる。4人の距離の近さはこのアンプラグド編成あってのことだろう。このセクションでは特別ゲストが登場することもJILLから発表され、いやがうえにも期待が高まる。
演奏に入る前には、2022年に全国の重要文化財施設を中心とした会場で『【ARE YOU EXPRIENCED?】PERSONZ neo ACOUSTIC SESSION』と題したアコースティックライブ・ツアーを開催したこと、そして2024年3月からは『HAPPY BLOOMING TOUR PERSONZ neo ACOUSTIC SESSION』と銘打ち、通常のバンド・サウンドとは一味違った“ネオアコースティック”ライブ・ツアーを開催することを発表。前回も行なった京都文化博物館 別館ホールやお馴染みの横浜赤レンガ倉庫などに加え、今回は奈良・東大寺境内の金鐘ホールや福島の大和川酒造 昭和蔵など、引き続き歴史的建造物の空間独特の響きの中で極上の“ネオアコースティック”サウンドをお届けするという。この日のアコースティック・セクションはその前哨戦、『HAPPY BLOOMING TOUR』の大いなる予告篇といった趣だ。
1曲目は「TRIUMPH OF LOVE」(2015年)。言うまでもなく24年振りとなる日本武道館公演を目指して生み出されたアンセムであり、困難なときでも希望を見失わず、自分自身を信じ続けることの大切さを唄う歌のテーマは、世界的なパンデミック、紛争の勃発、気候変動など目まぐるしく変転し続ける予測不能な時代にこそ響く。JILLは1番を唄い終えると観客に手拍子を促し、会場が一体感に包まれる。本田は時折、後方へ向いてプレイ。藤田はまるでキーボーディストのような風情で卓を叩きまくっているのが面白い。渡邉は黙々と重低音を奏でてアンサンブルの屋台骨を支えることに徹しているが、会場全体を見渡しながら時折微笑んでいるのが分かる。従来のバンド合奏と比べて音がよりシンプルとなり、アンプの増幅などごまかしも一切効かないアコースティック編成でここまで重厚なアンサンブルを聴かせるのだから、積み上げてきた39年のキャリアは伊達じゃない。ナチュラルなアコースティカル・サウンドでも不屈のロック・スピリットがにじみ出てしまうのは、PERSONZがPERSONZたる所以だろう。また、JILLが「アコースティック・セットのアレンジをどうするかが今回のライブのキモで、だいぶ時間をかけて臨みました」と話していた通り、原曲の良さを損なわぬアレンジがどれも秀逸だったことを明記しておきたい。
それは、本田と渡邉のコーラスが美しい「PRECIOUS LOVE」(1990年)も同様だった。今なお止むことのないウクライナとガザの戦乱、それを伝える凄惨なニュースを見ると毎日胸が痛むというJILLのMCから曲に入り、この混沌の時代に置き換えても何ら変わらない、この世における本当に尊いものとは何なのか? という歌の真髄が伝わる。それは端的に言えば「世界に平和を」というメッセージなのだが、バブル景気全盛の時代に書かれた「PRECIOUS LOVE」の歌詞が30数年後により現実味を増すとは、何とも皮肉で悲しい。だからこそこれからもずっと唄い継いでほしい一曲だと言える。
同じく5thアルバム『PRECIOUS?』収録の「PRIVATE REVOLUTION」(1990年)も今の時代に呼応する曲なのか、“ベルリンの壁”というワードは出てくるものの、古めかしさは感じない。2020年、コロナ禍になったときにこの曲をスロー・テンポでやってみようと考えられたアコースティック・アレンジは、いつかこの形式でレコーディングして残してほしいと思うほどの逸品。本田の切ないギター・ソロも短いながら気高く美しい。終盤、JILLは椅子から立ち上がり、花道で熱唱。格段にスケールアップしたその歌唱力を聴くにつけ、PERSONZが常に最善の更新をし続けるバンドであることを実感する。
アコースティック・セット4曲目で、1人目のゲストが登壇。
モデル、歌手、俳優と幅広く活躍し、『みんなで筋肉体操』の出演などで知られる當間ローズは赤いスパンコールのジャケットを身に纏い、登場するなりJILLと熱く抱擁。イタリア、ブラジル、日本の血を引き、ポルトガル語、日本語、英語、スペイン語を駆使する當間とは、“あの曲”をラテン・テイストでデュエットするのが良いのではないかとJILLは思案。そんなMCに導かれて披露されたのは、燃え上がる恋を描いた情熱的なラブソング「月の輝く夜に」(2018年)。當間との縁を繋いだ京都の陶芸家、冨金原塊(工房えんじゅ)が制作した、お馴染みのシルバー・ムーンのオブジェをJILLが掲げながら唄う。當間は2番の平歌をポルトガル語で独唱、サビもポルトガル語でJILLとデュエットする。2人の迸るパッションのぶつかり合いをフロアも強い手拍子で盛り立て、終盤のJILLと當間の歌と身振りの掛け合いは耽美かつ妖艶で絶品だった。最後に2人は再びハグし合い、鳴り止むことのない盛大な拍手喝采が場内に響き渡った。
続いて「クリスマスは終わってしまったけれど、インスタライブでちょっと唄ってみたらやっぱりいい曲だなと思って…やってみようと」と、PERSONZ初のクリスマス・ソング「BECAUSE THE HOLY NIGHT」(2011年)が夜景の映える場内で披露される。イントロから鳴り響く手拍子、ハンドウェーブする観客も見受けられる。
「ちょっと早いけどハッピー・ニューイヤー!」と唄い終えた後、2人目のゲストが登場。
4月に行なわれた『NAONのYAON 2023』で同じステージに立ちながらも直接の共演はなかった千秋が舞台袖から現れる。ピンクのベレー帽、鮮やかな緑のチュールドレスにピンクとホワイトのボーダージャケットという洗練された出で立ち。なお、JILLがこの日着用していた赤いチュールドレスも千秋のブランド「エリアCC」のものだという。千秋は以前、自身のYouTubeチャンネルで「DEAR FRIENDS」(1989年)のカバー動画を公開していたが、高校生のときに軽音学部に所属してPERSONZのコピー・バンドをやっていたとのこと。「どんな曲をやってたの?」というJILLからの問いに「『MIDNIGHT TEENAGE SHUFFLE』(1987年)とか…」と千秋が答えると、「じゃあやってみよう!」といきなり「MIDNIGHT TEENAGE SHUFFLE」が演奏される。予定外の即興演奏に千秋は慌てふためくも、スマホで歌詞を検索して唄う。これには観客も大いに盛り上がり、千秋も「『きっといつかは夢をかなえる』という歌詞があるけど、(PERSONZと共演するという)夢が叶った! あの頃の自分に教えてあげたい!」と話し、感極まっている様子が窺えた。
興に乗じて「他にはどんな曲を?」とJILLが訊けば、千秋は「『FREEDOM WORLD』(1987年)とか…』と答え、またその場で「FREEDOM WORLD」が即興演奏される。今度はご丁寧に本田のコーラス付きだ。「凄い! いきなり言って何でもやれる!」と千秋は興奮気味に語っていたが、叩き上げバンドが演奏技量の凄まじさをさらっと見せる姿が粋に感じられるパートでもあった。そんな贅沢すぎる余興を経て、肝心のコラボレーションは「DEAR FRIENDS」(1989年)。それもラテンボッサ風とでも呼べば良いのか、千秋をイメージしたという可愛らしいアレンジが施されたレア・バージョンだ。「そばにいて いつも待っててくれる」と唄う場面ではJILLと千秋が肩を組む姿も。最後に2人は抱擁、「夢を叶えるためにYouTubeやブランド運営など全力で行動するのは凄い!」とJILLは千秋の実践力の高さを称賛する。
篠笛の玉置ひかりも、當間ローズも、そして千秋も、みな縁が繋がって同じステージに立てていることをJILLは力説。数えきれない無数の事象が関係し合い、成り立つ出会い。もし無数の事象が一つでも欠ければまた違う出会いになったかもしれないし、そもそもその出会い自体すら存在しなかったのかもしれない。巡り会えた出会いは決して当たり前のことではないし、私たちがこうして日々生活できていること自体、幾重の生起が重なった結果であり、これもまた決して当たり前のことではない。だからこそ尊い。当たり前のように感じる日常も、繰り返しのように思える人生も、実に尊い。そんなつい忘れがちな大切なことを、PERSONZの歌はいつも教えてくれる。
アコースティック・セット最後の曲は、藤田が「希望の曲ですよね」と話した「DREAMERS」(1989年)。JILLいわく「ビートでバンバンやっていたのをバラード・アレンジで」ということで、オーディエンスも手拍子で応える。アレンジの妙もさることながら、本田と渡邉のコーラスも楽曲の優美さを高めている。いつの日かオーケストラとの共演が実現することがあれば、たとえばこの「DREAMERS」はロックとクラシックが融合した至高の一曲となり得るのではないか。
以上全7曲、約1時間に及ぶ熱演。本来ならこの第1部だけでも充分に素晴らしいエンターテイメント・ショーなのだが、2023年最後、究極の“Rock Party”はまだまだ続く。
“THE SHOW MUST GO ON”──それでもショーを続けていく決意表明
15分の休憩中に、張り出し舞台の後方席(上手エリアと下手エリア)が向きを変え、最前席に。これで全席がメインステージを向く形となる。18時44分に場内が暗転、ステージのバックスクリーンに今回のツアー・タイトルが投影される。続いてメンバー1人ずつ写真と名前が映し出され、個別に演奏を披露していくという小粋な演出。渡邉、本田がそれぞれ登場した後、もはやお馴染みのゲスト・プレイヤー、鍵盤奏者のおおくぼけい(アーバンギャルド)が登場。ユニセックスな装いでショルダーキーボードを振りかざして存在感を大いに発揮する。藤田が現れ、おおくぼが拍手をさらに大きく! と手振りで煽る。最後にわがロックンロール・クイーン、冠姿のJILLが神々しく降臨。役者は揃った。待ちに待ったバンド編成のライブの始まりに、怒涛の大歓声と共にフロアは総立ち。バンド・セットの序章を飾る「DRAGON LILY」(2006年、今回は“大感謝祭ver.”)の合奏が本格的に始まると、「ヘイ! もっともっともっと! カモン!」とJILLが観客を挑発する。
2024年は辰年、ドラゴンイヤー。結成40周年へ向けたキックオフ・ライブのイントロダクションとしてこれほど相応しい曲はないだろう。続く「SLEEPING BEAUTY」(1993年)では、本田がピート・タウンゼントを彷彿とさせる、右腕を大きく振り回しながらコードを弾くウィンドミル(風車)奏法を披露。JILLは冠を外し、花道を乗り越えて張り出しのステージへ向かい熱唱を続ける。 「さあ、ここからは“イェイ! イェイ!”セクション、“イェイ! イェイ!”ライブです!」とJILLが改めて盛大なパーティーの開催を宣言し、おおくぼけいを紹介する。「次は彼のキーボードが引き立つ曲を…」と、切なく疾走するメロディアスな曲調の「JUSTIFY」(2002年)が披露される。ビリー・プレストンが加わることでピリッと引き締まるビートルズのアンサンブルに似た相乗効果、それに近いものがこの日のPERSONZ+おおくぼけいには感じられた。ただし、戸川純や頭脳警察、大槻ケンヂなど数々の大御所ミュージシャンとの共演を果たしてきたおおくぼの自己定位は、主役の特性を最大限引き出すことに徹し、自身は終始引き立て役を貫く在り方だ。もちろん代替不可の個性は発揮するものの、必要以上に自分色に染め上げない。そのバランスと距離感が絶妙だからこそ、おおくぼにはサポート依頼のオファーが後を絶たない。
ここでJILLが一旦、舞台袖に捌ける。暗転の中でレジスターと硬貨の効果音が鳴り響き、ピンク・フロイドの「MONEY」を喚起する気怠いムードのインストゥルメンタルが奏でられる。華美なハットにサングラス、JILL自作のMoney帽子とストール、ゴールドのマネーガンを持って、「FUNNY MONEY」(1988年)のイントロが。なるほど、そう来たか。JILLが持参したトランクをバーンと開け、そこに入っていた紙幣の束を勢いに任せて客席へ向けて撒き散らす演出にも納得する(ちなみにその紙幣は、各メンバーの肖像画があしらわれた100ドル紙幣だったようだ)。
年末を騒がせた、政治家の政治資金パーティーをめぐる一連の問題を念頭に置いたのか、「世の中、カネ、カネ、カネ…と言ってますけど、私たちは清く正しいロック・バンドです!」とJILLが高らかに宣言。今年ようやく実現できたツアーを誰一人倒れることなく完走できたことをオーデェインスに感謝し、労をねぎらう。そして「みなさん、今日のスペシャル・パーティー、楽しんでいますか? 懐かしい曲を行きます!」と、時代は一気に36年前へとプレイバック。ファースト・アルバム収録の「REMEMBER」(1987年)のイントロが奏でられ、一際大きな歓声が巻き起こる。客席の大部分を占める、今や日本社会の支柱となる世代がただ夢見ていた“Eyes Of Children”の時代へ戻れる時間だ。
そのまま矢継ぎ早に「LUCKY STAR」(1987年)へと繋ぎ、夢のプレイバックは止まらない。JILLは右腕と左腕を交互に突き上げ、観客もそれに応えるように拳を突き上げながら、間奏は嵐のようなOiコール。不朽不滅のロックンロール・ナンバーは、広大なイベントホールをひとたび狭小なライブハウスへと豹変させる力を持っている。本田が渡邉に駆け寄り、互いにキメポーズを取り合うのも次世代へ受け継がれるべき清く正しいロックの様式美だ。 「6月からのツアー、今まで眠らせていた曲をどんどんやります! 春のアコースティック・ツアーはノリの良い曲もやります! 『I AM THE BEST TOUR』に来てくれてどうもありがとう!」
JILLが改めて観客に礼を述べ、ガムランの音色に導かれて「DREAMERS ONLY」(2015年)が始まる。不安な夜を塗り替えて、砕けない夢を夢見て、傷つき倒れそうでも立ち上がり挑んでいく。「自分を信じる心 抱きしめて」。そう唄われる「DREAMERS ONLY」は癒し系ならぬ肥やし系、心の糧となる歌だ。そう考えるとPERSONZの歌はどれも唄うお守りなのかもしれない。
老いも若きもOiコールで拳を突き上げ、興奮冷めやらぬなか、“B, B, E-S-T, B-E-S-T, Go!”という今やすっかりお馴染みとなったリフレインが聞こえてくる。70年代の洋楽を熱心に聴いていた世代はニヤリとするチャントだ。本編最後は本ツアーを象徴する一曲、「I AM THE BEST」(2020年)。比較対象はどこかの誰かではなく、常に自分自身。別に大きな夢じゃなくたっていい。どんな些細なことでもいい。昨日より今日。今日より明日。ほんの少しの伸びしろでも自己ベスト記録を自分らしく更新できればそれで充分。そんな願いにも似た思いをJILLは“I AM THE BEST!”のリリックに込めて唄う。鳴り止まぬ“B, B, E-S-T”の手拍子。バンドは最後の力を振り絞って渾身のプレイを聴かせ、JILLは張り出しの舞台まで詰めかけて最後の最後までオーディエンスを煽り、終幕と相成った。忌々しいコロナ禍を経て3年越しのツアー開催という悲願のリベンジを果たしたことの喜び、達成感をバンドと観客が共に分かち合えた瞬間だった。
当然の如くアンコールを求める歓声が鳴り響くなか、まずはJILLのみが登壇し、メンバーを1人ずつ呼び込む。「今日はアコースティックに通常のバンド・セットといろいろ楽しんでもらえたと思いますが、僕も全力で楽しんでいます」(藤田)、「今日はステージから遠い客席も張り出しのステージだと間近になって、そういう変化の面白さもこうしたライブならでは」(本田)というコメントの後、渡邉からは今日のライブがニコニコ生放送で生中継されていることが改めて伝えられ、さらにニコ生が2024年、PERSONZの40周年を密着することを発表。ニコ生のスタッフに熱心なPERSONZのファンがいるらしく、その縁で実現したという。ここで待望の新曲「FLOWER OF LOVE」を披露するのも良い流れだった。
2024年3月からのアコースティック・ツアーが『HAPPY BLOOMING TOUR』(“BLOOMING”=“咲く”)、6月からの40周年記念ツアーが『40th FLOWERS』と命名されているように、PERSONZの40周年におけるキーワードは“FLOWER”のようだ。「これからもバンドを続けて花を咲かせたい。ずっと音楽を続けていたらみなさんという花が咲いてくれました。みなさんがPERSONZの曲を育ててくれた。愛を持って育ててくれた」。
そう語るJILLは、この「FLOWER OF LOVE」を1月25日にデジタル・リリースし、それ以降、毎月新曲を届けようと考えていること、それが溜まれば1枚のアルバムにしたいと考えていることを告げた。そうして披露された「FLOWER OF LOVE」は、如何にもPERSONZらしく実にポジティブな、聴き手を鼓舞するように快活なナンバー。「自信を持って良い曲だと思います。レコーディングのときに思わず感極まった」とJILL自身が語るように、PERSONZの新たなクラシックとなる風格をすでに兼ね備えた一曲と言えるだろう。花が咲くまでには時間も手間もかかる。種子を蒔き、地に根を張り、芽が出て、空へ向かって茎を伸ばし、花が咲く。その長い過程では水や栄養を絶えず与えることも大事なら、育て続ける思いや根気もまた大事だ。骨の折れる作業には違いないが、だからこそ咲き誇る花は美しい。ただし花の命は短く儚い。それは儚さゆえの美しさとも言える。しかも同じ品種の花でも花びらと葉の位置はどれも異なり、1本たりとも同じ花は存在しない。1本1本違う花。でもどれも美しく咲き誇る花。開花するまでに七転八倒する労苦と長さに比べて咲き乱れる時間がとても短い花。なんだかわれわれ人間の営みみたいではないか。
閑話休題。JILLがおおくぼを呼び込み、おおくぼにより「HAPPY BIRTHDAY TO YOU」が奏でられ、ステージにバースデー・ケーキがサプライズで持ち込まれる。翌日(12月31日)に62歳の誕生日を迎える本田毅を演者も観客も一斉でお祝いする。これで1月にJILLが誕生日を迎えるまでは、JILLが63歳、本田が62歳、藤田が61歳、渡邉が60歳と、きれいに1歳ずつ離れるのだという。「PERSONZは大器晩成型なのかな? 今は何も怖いものがない。みんなでハッピーになりましよう!」とJILLが話し、“ラララ…ララ…ラララ…”と観客とのコール&レスポンスを経て披露されたのは、オープニングで披露された音頭ではなくオリジナルの「BE HAPPY」(1988年)。JILLは再び張り出しステージまで駆けつけて絶唱し、本田が渡邉のもとへ駆け寄って一緒にジャンプしながらプレイする様が微笑ましい。場内の揺れが凄い。
初期楽曲の無垢なパワーが聴き手を無垢の笑顔にして無邪気に踊らせるのだろう。その後、「これから大晦日、正月を迎える大変な時期に来てくれてありがとうございます」と語ったJILLは、この2023年が数多くのバンド仲間が他界した悲痛な1年だったことを明かした。高橋幸宏、坂本龍一、鮎川誠(シーナ&ロケッツ)、PANTA(頭脳警察)といった先輩格、櫻井敦司(BUCK-TICK)やISSAY(DER ZIBET)、HEATH(X JAPAN)といった共にバンドブームを牽引し続けた同世代、チバユウスケ(The Birthday, THEE MICHELLE GUN ELEPHANT)や恒岡章(Hi-STANDARD)といった後進のバンドマンたち。
「今年ほど死を身近に感じた1年はなかった」とJILLは心情を吐露した。
「正直、自分たちだっていつまでこのバンドを続けられるかわかりません。でも、もし私がどこかで倒れて二度とバンドをやれなくなったとしても、そこで悔いがないと言い切れるバンド活動を普段からしていたい。だから来年もまた…私たちに会いに来てください!」大歓声で応えるオーディエンス。そのリアクションを受けてJILLは続ける。「言霊ってありますからね。ここで言っておきます。私は100歳まで唄い続けます!」。
そう高らかに宣言し、披露されたのは「THE SHOW MUST GO ON」(1993年)。ご承知の通り、本田の脱退後に布袋寅泰や服部隆之の助力を得て制作された7thアルバムのタイトルトラックだ。この曲を今日この場でプレイすることこそ数多くの仲間たちを見送ってきた彼らならではの大いなる決意表明であり、志半ばで倒れた仲間たちへのレクイエムであり、この日のライブにおけるハイライト、一番の見せ所に思えた。JILLもそれに相応しい声の張り上げを聴かせ、尋常ならざる歌唱力の高さに圧倒される。
唄い終えたJILLは、こう語った。
「その時代によって歌の解釈は変わるものですね。1993年に『THE SHOW MUST GO ON』を書いたときはこの先どうなるんだろう? という不安で一杯だったけど、今日はどこまでも行くぞ! バンドはまだまだ続くぞ! という思いです」。バンドが本格始動する前から切磋琢磨してきたかけがえのない仲間が違う道を歩むことになり、失意のどん底に叩きつけられ、それでもショーは続けなければならない、一度始めてしまったら何があっても中止できないと何とか軌道修正していたあの頃とは違う。辛酸を舐めた過去も、辛抱強く友を待ち続けて再び合流し、“RELOAD PROJECT”の一環として24年後に4人で『THE SHOW MUST GO ON』を再構築するという明るい未来に塗り替えられた。それもPERSONZという屋号を決して下ろさなかったがゆえだ。まさに継続は力であり、バンドの歩みを止めなかったからこそ夢の断片を形にできた。耐えて咲かせる花もあることを、自称・大器晩成型のPERSONZは身に沁みて理解している。
さて、宴もたけなわだ。3時間半に及ぶ究極の“Rock Party”の締め括りは「DEAR FRIENDS」(1989年)。千秋と當間ローズを呼び込み、1番の平歌を千秋が、2番の平歌を當間がそれぞれ独唱。間奏のギターソロで本田が初めて張り出し舞台へ駆け寄り、終盤の“Wow, wow, wow, my best friends”の大合唱では、JILL、千秋、當間の3人が張り出しへ出向いてフロアとの境界線をなくす。全席から届く“Wow, wow, wow”、圧倒的一体感。「2024年もまた一緒に唄おうね!」というJILLの掛け声と共にアウトロへ加速、大団円を迎えた。 最後は張り出しステージで記念撮影。「良いお年をお迎えください! 来年また会いましょう!」とJILLが挨拶し、PERSONZが親愛なるオーディエンスへ贈る2023年最大の祝典は幕を閉じた。
“THE SHOW MUST GO ON”、人生もショーも悔いの残らぬように最後まで最善を尽くして全うしたい。結成40周年の節目に向けてそう宣告し、表現者としての覚悟を明示したPERSONZの2024年は、いつか大輪の花を咲かせる日を夢見て絶えず疾走を続けるのだろう。寒苦に耐えて咲く梅や椿のような美しさ、可憐さ、揺るぎない強さを身に纏い、PERSONZの自己ベスト記録更新は続く。(文:椎名宗之/写真:アンザイミキ)
- 1
- 2
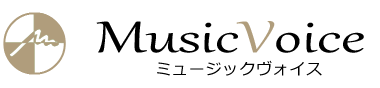



















 PERSONZ、ネオアコースティックコンサートを開催 JILL「すごく胸に来たライブでした」
PERSONZ、ネオアコースティックコンサートを開催 JILL「すごく胸に来たライブでした」 PERSONZ、結成40周年アニバーサリーイヤーに花を添えるツアーが決定
PERSONZ、結成40周年アニバーサリーイヤーに花を添えるツアーが決定 本田毅、約4年ぶりのバンドスタイルライブを東京で開催
本田毅、約4年ぶりのバンドスタイルライブを東京で開催 PERSONZ、39周年を締めくくるライブ「Year-End Ultimate Rock Party」開催
PERSONZ、39周年を締めくくるライブ「Year-End Ultimate Rock Party」開催 PERSONZ、有楽町ヒューリックホールで見せた40周年への期待感
PERSONZ、有楽町ヒューリックホールで見せた40周年への期待感 PERSONZ、楽曲至上主義を貫く生粋のライブバンドが自己ベストを更新するリアルタイムの物語
PERSONZ、楽曲至上主義を貫く生粋のライブバンドが自己ベストを更新するリアルタイムの物語 PERSONZ、幻のツアーが再び始動 新たな形で実施決定
PERSONZ、幻のツアーが再び始動 新たな形で実施決定 PERSONZ・JILL、soloライブ開催を発表
PERSONZ・JILL、soloライブ開催を発表 PERSONZ「ギネスに載るまでやりたい」ビルボードライブ横浜公演レポート
PERSONZ「ギネスに載るまでやりたい」ビルボードライブ横浜公演レポート