PERSONZ、楽曲至上主義を貫く生粋のライブバンドが自己ベストを更新するリアルタイムの物語

『PERSONZ I AM THE BEST TOUR 2023』5月7日の模様
PERSONZがさる5月6日と7日に、ツアー『PERSONZ I AM THE BEST TOUR 2023』の初日公演2daysが開催された。このツアーは当時5年ぶりに発表されたオリジナル作品『I AM THE BEST!』に伴うツアーとして2020年に企画されたものの、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、2021年に無念の中止に。それがバンド結成39周年を迎える2023年、さらにスケールアップしたPERSONZが“BEST”な楽曲をリストアップして全国を回るという新たな形で開催されることが決定した。
声出し緩和により、バンドと観客が一体化して生まれる多幸感をあらためて実感
会場は、横浜赤レンガ倉庫1号館の3階ホール。PERSONZが同会場でライブを行なうのは、昨年5月の『PERSONZ THE BEST: GREATEST SONGS_ver.02』以来、1年ぶり。赤レンガ倉庫は、明治末期から大正初期にかけて国の模範倉庫として建設されたレンガ造りの歴史的建造物であり、『【ARE YOU EXPRIENCED?】PERSONZ neo ACOUSTIC SESSION』で全国の重要文化財施設などの異空間でライブを行なうという趣向を凝らした企画を繰り広げてきた彼らに相応しい会場と言えるだろう。
新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが季節性インフルエンザなどと同じ5類へ移行、感染対策は個人の判断に委ねられることになった5月8日を目前に控えた今回のライブは、マスク越しではありながらも久しぶりに観客の声出しが許可されたもので、場内が暗転し、威風堂々としたSEが流れるや地鳴りにも似た歓声と声援、惜しみない拍手がステージへ向けられる。コロナ禍が完全に終息したわけではないが、この声出し緩和はやはり脱コロナに向けた日常へ戻そうとする動きが進んだことの表れに思えた。
24年振りの武道館公演へ向けてファンと育んだ2015年のアンセム「DREAMERS ONLY」、観客と一緒に“WOW WOW”とシンガロングしたくて選ばれたという2008年発表の『HEART OF GOLD』から「THE ONLY ONE」、1991年発表のシングル「TRUE LOVE ─涙にぬれて─」と畳みかけるように名曲の数々を聴かせるが、フロアのリアクションが従前に近い形に戻ってきたせいか、バンドはとてもやりやすそうに鉄壁のアンサンブルを繰り出す。エレキギターとエフェクターを駆使して色彩豊かな音色を自在に奏でる本田毅、躍動感溢れる粒だった低音を鷹揚自若に奏でる渡邉貢、バンドの屋台骨として屈強のリズム&ビートとダイナミクスを束ねる藤田勉。彼らに導かれて発せられる伸びやかで艶やかなJILLの七色の歌声。それらが渾然一体となってホール全体に響き渡る。アンプから浴びる爆音轟音と風圧、こればかりはネットを介した配信ライブでは決して味わえないものだし、現場に足を運んだ人にしか享受できないものだ。だからこそ観客同士で、あるいはステージ上の演者と共に共犯関係のようなものが生まれる。
久しぶりのツアー開催に声出し解禁という特別な一夜、もとい二夜に華を添えるべくゲストとして登場したのは、アーバンギャルドの鍵盤奏者であるおおくぼけい。今年3月に行なわれたJILLの6年ぶりのソロライブ『singin'』でも見事な客演を果たし、その際の実力を買われて今回の出演につながったという。舞台袖から飛び跳ねてステージに現れ、どこかフェミニンな雰囲気を身にまとったおおくぼの登場には面喰らったかもしれないが、その装いとは裏腹の演奏技術とパフォーマンス能力の高さに舌を巻いた観客も多かったのではないか。
個人的には、2006年発表のスタジオライブDVD『DRAGON LILY』に収録された「IN THE NAME OF LOVE」というレア曲、JILLがおもちゃのハンドルでイントロにいざなう「BACKSEAT DRIVER」、「水に映った月」という『砂の薔薇』の収録曲を聴いて、このライブでおおくぼに白羽の矢が立った真意が窺えた。シーケンサーを同期させた通常のライブではない生の鍵盤の迫力や真髄を聴かせたいという狙いももちろんあっただろうが、1994年発表の『砂の薔薇』は本田不在時の作品であり、矢代恒彦のキーボードや鈴木“コルゲン”宏昌のピアノを大胆にフィーチャーしていた。つまり、もし本田が同作に参加していたならこんなサウンドになっていたはずだという29年越しの試みだったとは言えまいか。
もっとも「水に映った月」はJILLとおおくぼのデュオ形態だったわけだが、間違いなくこの日のセットリストの白眉だった。水面の月のようにいくら追い求めても決して届かぬ切なる思いを歌に託したJILLの表現力もさることながら、その歌にしっかりと呼応するおおくぼの情感豊かな独奏は思わず息を呑むもので、戸川純やPANTA(頭脳警察)といった大物ミュージシャンがこぞっておおくぼを重宝し、共演を望む理由がよく理解できた名演だった。
同じく月夜を主題にした「MOONSTRUCK〜月の輝く夜に」(2008年に発表された『HEART OF GOLD』収録曲)に連なる流れも非常に粋な構成だったし、PERSONZの楽曲に内包する抒情性溢れる作風が際立ったパートと言えるだろう。
余談だが、この日は奇しくもフラワームーン(5月の満月はアメリカの農事暦でこう呼ばれる)。ライブの帰路に万国橋から見えた、暮れゆく夜空に溶け込むオレンジの月がひときわ綺麗だった。
跳ねる鍵盤が曲を終始牽引する「悲しみの天使」もまた『砂の薔薇』の収録曲であり11枚目のシングル曲で、これをもっておおくぼは送り出されるが、通常編成に戻った後も『砂の薔薇』収録の「I NEED YOU」が披露されるというレアな選曲が続く。JILLは曲紹介の中で、『砂の薔薇』から先行してシングルカットされた「I NEED YOU」が当時ミナミスポーツのタイアップ曲に起用されたことを語りながら、応援してくれるファンのみんながいてこそのPERSONZであること、PERSONZにとってここに集まるみんながかけがえのない“必要”な存在であることを力説した。その思いはコロナ禍を経て、より強固なものになっただろうし、3年以上にわたり耐え忍んだ季節が終息を迎えつつある今、あらためてファンのみんなに伝えておきたかったのではないだろうか。
タイアップ繋がりで、テレビ朝日のニュース番組『ステーションEYE』のエンディング・テーマに起用された「FUTURE STAR」はご承知の通り、オリジナルは本田不在時に制作され、盟友・布袋寅泰がギターを弾いている。それに加え、同曲が収録された『THE SHOW MUST GO ON』(1993年6月発表)もまた鍵盤を全面的に取り入れた意欲作だったので、その時期の楽曲もおおくぼとのセッションに合いそうだと考えていたら、翌日にその考えが的中した(後述)。
本編最後は、1989年に発表された6枚目のシングルのB面であり、4枚目のアルバム『DREAMERS ONLY』収録の名曲「DREAMERS」。これもパナソニックのヘッドフォンステレオのCMソングに起用されたタイアップ曲だ。こうした耳馴染みのある有名曲を要所に据え、コアなリスナーほど歓喜するだろう知る人ぞ知る楽曲を中盤に挿入する絶妙な采配、バランス感覚が実に見事だ。「DREAMERS ONLY」に始まり「DREAMERS」で締めるのも乙な流れだし(ここまで一気に90分、あっという間だった)、硬軟織り交ぜたセットリストを一切弛緩することなく聴かせるバンドの技量、一体感にはやはり感服せざるを得ない。
鳴り止まぬアンコールに応え、あらためておおくぼけいを迎えて披露されたのは、2002年発表のシングル曲「SINGIN'」。「世界の風向きや 政治や宗教さえも/この歌で変えれはしないけれど/誰かの人生の ほんの少しの気持ちが/どこかで動き出すかもしれない」という冒頭の歌詞は、世界的なコロナ禍やロシアによるウクライナへの軍事侵攻を始めとする世界中の紛争や内戦などと直面する、2023年を生きるわれわれの胸を深く打つ。21年前の発表時よりもその歌詞を深刻に受け止めなければならない状況は悲しいものだが、誰しもが暗中模索するこの激動の時代に、日々の虚しさや絶望を拭いきれなくても明日を夢見て唄っていこう、重い扉を開けて共に歩き出そうと目前の観客へ投げかけるPERSONZの揺るぎない決意を感じずにはいられなかった。この「SINGIN'」をいま敢えて唄い継ぐことが今回の『I AM THE BEST TOUR』における主題であり本意なのではないかと感じたほどだ。
だが、そうした気高いメッセージ性も提示しつつ、あくまでポップでしなやかに我流を貫くのがPERSONZである。おおくぼを見送り、最後は1989年に発表された4枚目のシングル曲にして不動の4番打者的ナンバー「DEAR FRIENDS」、最新にして最強のポップチューンである「I AM THE BEST」をバンド単体で聴かせ、最新のPERSONZこそが常に最強であることを軽やかに主張してみせた。
ツアー再開に至るまで3年もの長きにわたり苦渋を強いられ、その間に刃を研ぎ続けることを忘れなかったPERSONZと、念願のツアー再開と従前のライブの在り方を待ち望んでいたオーディエンスのエネルギーが激しくぶつかり合い、互いの相互作用によって一期一会のライブ空間を生み出せる時が再来した喜びを噛み締め合う、多幸感に満ち溢れた一夜だった。
ポストパンクやニューウェイブを出自としながら生粋のエンターテイナーという独自のスタンス
ツアー2日目の7日(日)はゴールデンウィーク最終日だったが、あいにくの雨模様。前日の17時半よりもさらに早い15時開演だった。
1989年に発表された6枚目のシングルにして代表曲のひとつである「FALLIN' ANGEL ─嘆きの天使─」でオーディエンスの昂るハートを一気に鷲掴みにし、1990年に発表された5枚目のアルバム『PRECIOUS?』に収録された「MAYBE CRAZEE ─I Love You─」で本来は多目的ホールである空間を灼熱のダンスフロアへと一変させる。
その熱量を携えたまま加速するかと思いきや、2010年に発表された19枚目のオリジナル作『ROCK'A'THERAPY』収録の「MEDICINE」という意外な選曲が早くも登場する。世界で卵巣がん治療に承認されている抗がん剤を日本でも承認してほしいと卵巣がん体験者の会である“スマイリー”が署名活動をしていたことをJILLが知り、スマイリー代表の片木美穂さんがPERSONZのファンだった縁で「MEDICINE」というスマイリーの活動を応援する楽曲が生まれ、卵巣がん患者が治療薬の承認を求める中でこの曲が折れそうになる気持ちを奮い立たせる力となったのはご承知の通り。『ROCK'A'THERAPY』とは言い得て妙なタイトルで、JILLはMCでロックとセラピーは最強の組み合わせだと語る。あるイギリスの研究機関によれば、ライブを定期的に観に行くと寿命が約9年間延びるという研究結果もあるそうだ。真偽のほどは定かではないが、昨日、今日とここ横浜赤レンガ倉庫1号館に集まるフロアの観客が楽しそうに踊り、はしゃぐ姿を見るにつけ、音楽ライブに行く人は幸せを感じやすくなるという研究調査は決して間違っていないのだろうなと実感してしまう。
冒頭の3曲を終えてスペシャル・ゲストのおおくぼけいを迎え入れるのは、前日と同じ趣向だ。「DEAR FRIENDS」のB面曲であり、1989年に発表された3枚目のアルバム『NO MORE TEARS』に収録された、本田作曲による「BELIEVE」。JILLもMCで話していたが、本田のギターとおおくぼのキーボードは実に相性が良い。楽器の違いはあれど、浮遊感漂う夢心地の音色やエッジの効いた鋭角的な響きを巧みに繰り出す点、上物でありながら他のパートの良さを引き立たせる謙譲の美徳みたいなものが共通項としてあるように感じる。
続いて、14枚目のシングル曲であり、1996年に発表された10枚目のアルバム『GUARDIAN ANGEL』に収録された「BLUE HEAVEN」。まさに隠れた名曲と呼ぶに相応しく、こうした格別な趣きを持つライブで強い存在感を放つ一曲だ。これもまたオリジナルでは不在だった本田が演奏するとこんなふうに様変わりするのだと新たな気づきを与えてくれる。さらに言えば、現実の天気がいくら雨模様でも、心の中に曇ることのない青空を投影する力が音楽にあることをPERSONZの歌は教えてくれる。
初日は鍵盤がアレンジの要となった『砂の薔薇』の収録曲が数多く披露されたが、そうした作風への流れを生んだ『THE SHOW MUST GO ON』の収録曲もまた、おおくぼとのセッションパートにはおあつらえ向きではないか。そう前日に想像したことが、この日の中盤で具現化した。JILLの歌とおおくぼのキーボードだけで唄い奏でられた「恋せよ乙女」は言うまでもなく『THE SHOW MUST GO ON』収録曲で、この日のハイライトのひとつと言って良いだろう。
タイトルの出典元である「命短し恋せよ乙女」は、大正時代の1915年に発表された歌謡曲「ゴンドラの唄」の中で用いられたフレーズ。1915年と言えば第一次世界大戦の真っ只中であり、「ゴンドラの唄」には「明日の月日はないものを」「赤き血潮の冷えぬ間に」といった刹那のニュアンスを感じさせる歌詞もある。つまり、乙女と呼ばれる若い季節はとても短く、今は戦争のさなかで何が起こるかわからないのだから、本気の恋を精一杯楽しむべきだという若き女性へ向けたメッセージが込められている。そうした歴史的事実を知った上で「恋せよ乙女」の歌詞を書いたというJILLのMCを聞き、今のウクライナやロシアで生活する若き女性のことを思わずにはいられず、時代を超えた歌の普遍性、時流に流されない歌の強さを実感した。
結成20周年を記念して2004年にリリースされた一作である『mirrorball』の表題曲「MIRRORBALL」(「恋せよ乙女」からのインタールードも秀逸だった)、1995年にリリースされた13枚目のシングル曲であり9枚目のオリジナルアルバム『OURS』収録の「STAY AS A FRIEND ─友達のままで─」というこの日のトピックスと言うべき滅多にない選曲が続き、おおくぼが送り出される。
2日にわたり繰り広げられたPERSONZとおおくぼによる忖度なしのセッションを体感して思ったのは、“RELOAD PROJECT”の一環として、本田が不在だった『THE SHOW MUST GO ON』と『砂の薔薇』の収録曲を今の4人で再録し、ゲスト・プレイヤーとしておおくぼけいが参加したなら、実に今日的なPERSONZを堪能できるのではないかということだった。それほど本田不在期の楽曲の本田を含めたバンドの再現、そこにおおくぼが加味した2日限りの即興“RELOAD”はとても素晴らしいものだったと断言できる。
その後は一気呵成に、踊る阿呆に踊らぬ阿呆、同じ阿呆なら踊らにゃ損損、の時間だ。『PRECIOUS?』収録の「PRECIOUS LOVE」、1994年に発表された12枚目のシングルであり、『OURS』にも収録された「VENUSの憂鬱」(オリジナルにはない、U2を彷彿とさせる平歌部分のギターリフが楽しい)という怒涛の流れの後、『NO MORE TEARS』収録の「TOKIO'S GLORIOUS」で本編の大団円を迎えた。
JILLと観客による張り裂けんばかりのコール&レスポンス、一体化する手拍子、うねるような床の振動にただただ身震いするばかり。見渡せば、今の日本社会の中枢を担っているのであろうミドル〜シニアエイジの紳士淑女が一心不乱に拳を突き上げて歓声を上げている。オーディエンスの年輪はそのままバンドが経てきた歳月と重なる。互いに切磋琢磨して生きてきたバンドも観客も、いまだ風の中や闇の中、手探りで輝きを探している。どれだけ風向きが強くても背中を押してくれる魂の歌を生み出すバンド、その歌を糧として生きるリスナーとオーディエンス。そのどちらかが欠けても成立しない。その共存、共犯関係は決して馴れ合いではなく、一期一会の数珠繋ぎのようだからこそ美しい。
アンコールでは再びおおくぼけいを呼び込み、不朽の名作である『DREAMERS ONLY』収録の「SINGIN' IN THE RAIN」を披露した。日々の喧騒を洗い流す讃美歌にも似たたおやかなこの曲を、実際にそぼ降る雨の日に体感できることもなかなかないだろう。そうした観客に向けた最大限の気配りと言うのか、徹頭徹尾楽しんでもらおうとするバンドのエンターテイメント精神を最後まで随所に感じた2日間だった。
この日も最後の最後は、「DEAR FRIENDS」と「I AM THE BEST」を披露して幕を閉じるフィナーレだった。今さら言うことではないけれども、PERSONZは実に多くの名曲を生み続けてきたバンドである。元来、ポストパンクやニューウェイブの洗礼を受けて頭角を現したバンドなのだし、もっと予定調和を蹴散らす活動を貫き、ライブのセットリストもより意表を突く構成にしても良いはずなのだ。そうでもしなければ、常に現役の最前線に身を置いて新曲を絶えず発表し続けるバンドにとっては埋もれてしまう楽曲が増える一方だ。たとえば「DEAR FRIENDS」や「7 COLORS(Over The Rainbow)」、「DREAMERS」といった代表曲を一切やらず、コアな選曲だけでライブを押し通しても許されるだけのキャリアを詰んだバンドであるにもかかわらず、彼らは決してそうした選択肢を選ばない。なぜか。それは彼ら4人がパンクを出自とした世代ならではの思考と嗜好と志向を内包しながらも、オーディエンスが望む期待に応えること、ファンに楽しんでもらうことを至上の喜びとする生粋のエンターテイナーであるからに違いない。そうでなければ、両日共に同じ演目のアンコール2曲を除き、初日と2日目に披露された全24曲に一切の被りがないなどというサービス過剰なセットリストをわざわざ考えるわけがない。
あらためて記しておきたいが、今回のフロアでの声出し緩和が実現したことで実感したのは、観客の歓声や声援なしにライブは成立し得ないということだ。後年、このテキストを読んだ人は「何を当たり前のことを書いているんだ?」と思うだろうが、そんな当たり前のことを当たり前のこととして享受できなかったのがコロナ禍以降の約3年だったのだ。
観客一人ひとりの人生と伴走してきたPERSONZナンバーのイントロが奏でられたときの、客席前後左右のどよめき、ざわめき。フロアの温度がグッと上がる瞬間。あれこそが生のライブの醍醐味だ。その感覚を久しく忘れていた部分があったし、そうしたライブでの共振、共鳴こそ生きる活力、滋養強壮となることを、この『I AM THE BEST TOUR』初日2daysでバンドとオーディエンスが思い出させてくれた。
ライブとは見ず知らずの隣の誰かと一緒に作り上げるもので(安易に群れず、馴れ合いを良しとしないのが個人的な流儀だが)、その一体感がステージへフィードバックする。そうした接触でのみ生じるライブのコミュニケーションは濃厚接触そのものを否定されたコロナ禍では成立し得なかった。だが、ライブハウスの逆襲はまさにこれから。ライブほど楽しい体験は他にないことを世に知らしめるメッセンジャーとして、39年にわたり生粋のライブバンドとして活動し続けるPERSONZほどの適任者はいないだろう。
ともあれ、“始まりを迎えるための1日”と“本当に始まりを迎える1日”を無事に終え、リベンジの火蓋は切って落とされた。次回、6月18日(日)高知県立県民文化ホール グリーンホール以降、8月26日(土)福岡 電気ビルみらいホールまでの10公演は、今回の2daysとは異なるセットメニューになるという。3月に渡邉貢が還暦を迎えたことでメンバー全員が60代となったPERSONZだが、バンドのグルーヴ感と円熟味はさらに増すばかり。結成以来、楽曲至上主義を貫く彼らのレパートリーには埋もれた名曲がまだたくさんあるし、それらが一曲でも多くライブで蘇生されることを願いたい。本ツアーは来年の結成40周年に向けた大いなる助走かつ序章であり、まだまだ日進月歩の勢いで進化し続けるPERSONZというリアルタイムの物語なのだ。
文:椎名宗之
写真:アンザイミキ
- 1
- 2
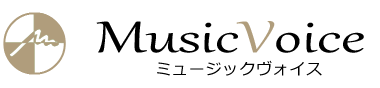

























 PERSONZ、ネオアコースティックコンサートを開催 JILL「すごく胸に来たライブでした」
PERSONZ、ネオアコースティックコンサートを開催 JILL「すごく胸に来たライブでした」 PERSONZ、結成40周年アニバーサリーイヤーに花を添えるツアーが決定
PERSONZ、結成40周年アニバーサリーイヤーに花を添えるツアーが決定 本田毅、約4年ぶりのバンドスタイルライブを東京で開催
本田毅、約4年ぶりのバンドスタイルライブを東京で開催 PERSONZ、“39周年”を締め括るロック・パーティー開催 千秋がゲスト出演し「DEAR FRIENDS」をコラボ
PERSONZ、“39周年”を締め括るロック・パーティー開催 千秋がゲスト出演し「DEAR FRIENDS」をコラボ PERSONZ、39周年を締めくくるライブ「Year-End Ultimate Rock Party」開催
PERSONZ、39周年を締めくくるライブ「Year-End Ultimate Rock Party」開催 PERSONZ、有楽町ヒューリックホールで見せた40周年への期待感
PERSONZ、有楽町ヒューリックホールで見せた40周年への期待感 PERSONZ、幻のツアーが再び始動 新たな形で実施決定
PERSONZ、幻のツアーが再び始動 新たな形で実施決定 PERSONZ・JILL、soloライブ開催を発表
PERSONZ・JILL、soloライブ開催を発表 PERSONZ「ギネスに載るまでやりたい」ビルボードライブ横浜公演レポート
PERSONZ「ギネスに載るまでやりたい」ビルボードライブ横浜公演レポート