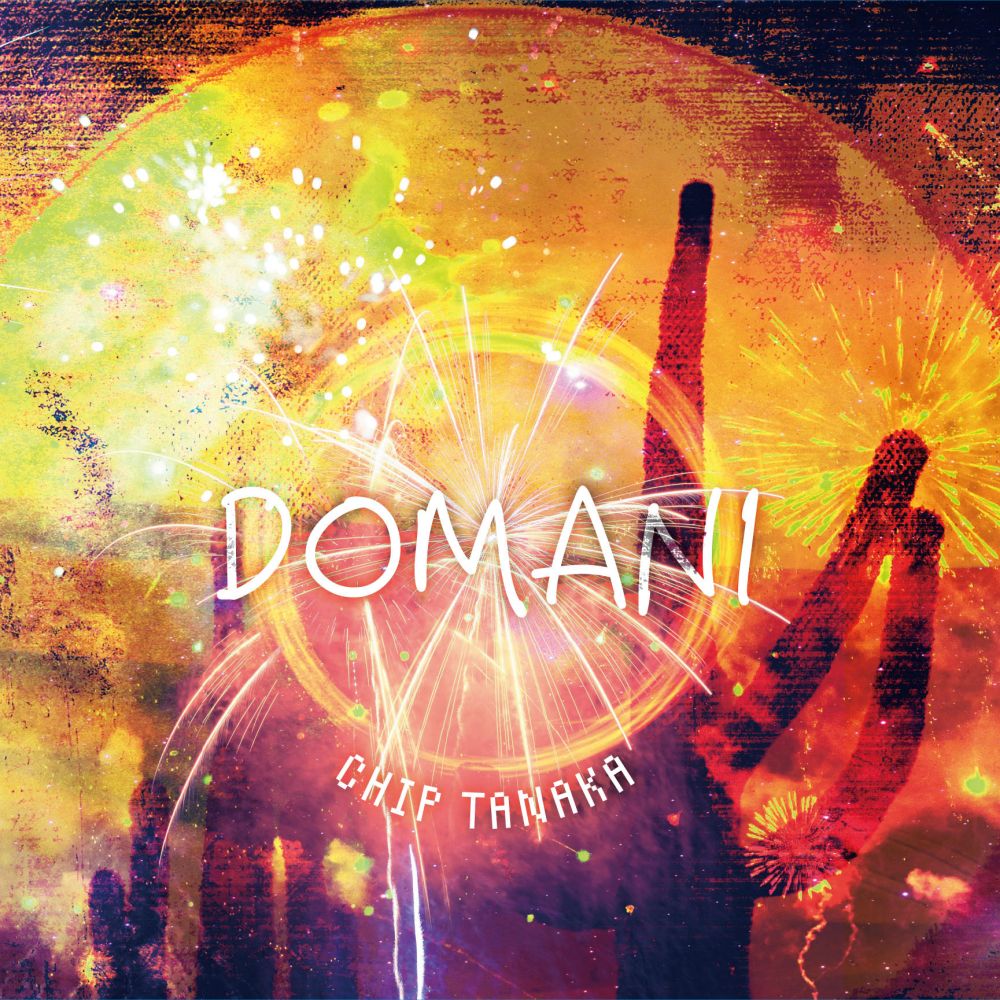- 1
- 2
1980年より任天堂のサウンドエンジニアとしてチップサウンドをゲームミュージックとして世界に広げたオリジネーターであり、作曲家としてはテレビアニメ『ポケットモンスター』の主題歌『めざせポケモンマスター』の作曲を手掛け、200万枚のヒットを記録している田中宏和(たなかひろかず)が11月17日、Chip Tanaka名義の3rdアルバム『Domani』(ドマーニ)をリリースした。本作『Domani』はコロナ禍、環境 問題などが渦巻く2021年、彼自身の未来と世界の未来を重ね、 変わるもの、 変わらないもの、存在の儚さ、夢などをテーマにした14トラックを収録。インタビューでは、『Domani』の制作背景から、ゲームミュージックを制作していた時に大切にしていたこと、歌ものに取り組む姿勢など多岐にわたり話を聞いた。【取材・撮影=村上順一】
身体を通して感じたことが音楽に影響を与えていた
――今作はどんなところからインスピレーションを受けて制作されたのでしょうか。
以前のアルバムは当時ライブ出演の回数が多かった事もあり、他の出演者の音とかそれこそVJが操る視覚イメージに触発されたり、そういう身体を通して感じたことが音楽に影響を与えていたと思います。特に一作目の『Django』はそんな風でした。でも、コロナ禍で動けなくなって、外に出ても近所の公園と自宅の行き来くらいで。その中で家で出来ることとして、昔好きで聴いていた音楽を改めてたくさん聴きました。なので、今作は身体で感じたものよりも、過去の様々なアーティストを耳で聞き蘇ってきた記憶とか、現在の耳で聞いた時の印象などが影響を与えてます。
――なんでもピンクフロイドの『狂気(The Dark Side of the Moon)』をよく聴いていたとSNSで発信されていましたね。
そうですね。中学の時にピンク・フロイドとイエス、あとロキシー・ミュージックが好きだったんですね。なぜかはわからないんだけど、イギリスのバンドが好きだった。あと、ピンクフロイドは『狂気』の他にも、『おせっかい(Meddle)』というアルバムも気に入っています。曲調も静かでコード進行もシンプルなものが多いのですが。
『狂気』はメイキングも見ていたので、制作背景とかも強く印象に残ってます。でも、それに寄せようとかというのはなくて、これまでChip Tanaka名義の作品は割とダンス系で四つ打ちのビートが多かったのですが、今回は割と8ビートの楽曲が増えてます。そこにChip Tanakaのこだわりの一つである矩形波を上手く活かしながら作っていきました。
――「Hourglass」はその要素が出ていますね。今作のアルバムタイトルは『Domani』なのですが、過去作も『Django』『Domingo』と“D”から始まるタイトルでしたが、これは狙って?
そもそもスペイン語の人の名前でつけてみようという発想があって。『Domani』はイタリア語の方が有名なんですけど、スペイン語でも同じ綴りです。『Django』には目覚めるという意味があって、60歳になって覚醒するというのが面白いなと思ってつけました。2ndアルバムは夜や深海、郷愁をイメージした曲が多く、静かなイメージがあったので『Domingo』休日、安息日という意味をもってきました。今回はパンデミックの最中、曲を作る中でなんとなく、未来、将来はどうなる? と感じた事もあり『Domani』としました。
――ご自身の中で挑戦的な部分もあったのでしょうか。
挑戦というのはないんだけど、一番気にしたのは、過去の2作品の印象を残しながらどう新しさを入れていくか、という点でした。今回は前作以上に声素材を使った曲とか、いままでになかったポップさも全面に押し出しました。
――今作の最後を締めくくる「1912」はTanakaさんの中でキーになる1曲とのことですが、その意図は?
リスナーの中でキーになるかはわからないんだけど、この曲に繋げるために他の曲を修正しながら構成していったというのがあります。アルバムとして聴いてもらうことが前提なんですけど。それこそ、ピンク・フロイドの『The Dark Side of the Moon』はレコードで聴いててA面終わると裏返してB面というように、そんなイメージを頭に描きながら全体を作っていきました。今はサブスクでバラバラに聴く人も多いと思うけど、アルバムをトータルで聴く良さもあるので。なのですが今そういう人は少数派かもですね(笑)。
――ちなみにTanakaさんはアナログの良さをどこに感じていますか。
音が耳に優しいところ、聴くときの所作かな。面倒臭いんだけどね(笑)。針も磨耗していくわけで、そろそろ変えたほうがいいのかな、でも勿体無いなとか思いながらコーヒー飲みながら聴くのが好きです(笑)。デジタルでも聴きますけど、ちゃんとスピーカーを鳴らして空気が振動して部屋に広がる感覚、体に響いてくる方が僕は好きですね。
――最近、私もレコードで聴くようになったんですけど、音の違いにビックリしました。
全然違うよね。でも、デジタルが悪いというわけではなくてこれは好みの問題で、どちらの質感が好きかどうかですよね。僕はいまだにカセットテープも好きなんです。レコードの良さ、CDの良さ、カセットテープの良さそれぞれあると思います。
「1912」に込められた想い
――アルバム『Domani』は裏テーマとかあったりしますか。
裏テーマという事ではないですが。さっき話した歌っぽい曲は「砂漠のサボテン」が歌っているイメージなんです。
――そのサボテンという発想が生まれたのは?
インスピレーションです(笑)。人間はコロナで苦しんでいるけども、サボテンはそれとは無関係に生きている、けれど、砂漠という厳しい環境で生きていているわけで、そんな風景が頭をよぎったんです。
――それで、「Cactus Chant」という曲があって。
ですね。「Fennec」や「Sandstorm」も砂漠のイメージを広げていった結果できた曲です。あと『星の王子さま』の著者であるサン=テグジュペリは空にずっと憧れていて、彼が初めて飛行機に乗った時、そこから空を飛ぶことの虜になった。サン=テグジュペリが亡くなる時も飛行機で行方不明になってしまっているくらい。タイトルの「1912」というのはサン=テグジュペリが初めて知り合いの人に飛行機に乗せてもらって空を飛んだ年なんです。
人は社会に生かされつつ、その未来は偶然も含め人の持つ夢や願望で形作られていると思うんですね。その事とサン=テグジュペリが空を飛んだ年を重ねて「未来」を表現しようと思いました。で、この「1912」でこのアルバムを締めたかった。それが自分の中での“Domani”だったんです。ちなみに2曲目の「Pacific」は海ですけど、飛行機から見えた海といったイメージもあります。
――オープニングの「GO→JUMP↑」もそのイメージと重なるところも?
これは、そのイメージではなくて自分のかつての仕事、ゲームミュージックということを体現した楽曲になっています。けれど主人公はサボテンという事にしました。この曲のPVもあるんですけど、その映像は今話した事を伝えて作ってもらいました。なので、PVを見てもらえれば納得してもらえると思います。音だけだとゲームっぽい音楽、Chip Tanakaだよねみたいな感じだと思うけど、映像ではアルバムの全体像が伝わったら良いなと思って。
――今作を制作するにあたって苦労されたところは?
作っていく中で似たような雰囲気の曲が出来てしまうところかな。どんな音を使ってもムードが似てしまって。
――今どのような環境で制作されているのでしょうか。
ソフトシンセを使って作業することが多いです。
――Tanakaさんの耳で聞いてもソフトシンセの完成度は高いですか。
問題ないですよ。ミニモーグのようなハードのアナログシンセと比べるとその存在感は全然違います。けれど、曲中にまぜて使う分には影響はあまり感じません。ハードシンセにこだわる方はまた別かもしれませんけれど。
同時発音数3音の制約 何が特徴なのかを考える
――あと、Tanakaさんがファミコンの音楽を作られていた時は、音源の性能で3音しか同時に発音出来ないという制約がありましたが、現在のように何音も重ねられることのメリット、デメリットは感じていますか。
使える数が多い、少ないというのはあまり気にしてないですね。当時は3音しか同時に鳴らせないというのがそもそもハードの仕様だったので、しょうがないです(笑)。少なかったら少なかったなりの特徴を出そうと努力しました。3音以内で可能な魅力的な組み合わせとかヴォイシングを色々試しました。自分はその仕様を作ったメーカーの人間だったので当たり前だと感じてましたけれど、外部の人は「たった3音しか鳴らせないの?」と思っていたかもしれないですね。
――音源自体もTanakaさんが作られていたんですか。
はい。ファミコンは複数人いましたが、ゲームボーイの音源は自分一人で担当しました。
――Tanakaさんから見て、制約がある中での表現として面白いなと思った方とかいましたか?
面白いというのは違うけど、すぎやまこういちさんの登場は業界に大きな影響を与えたのでは? と思いますね。すぎやまさんはゲーム中、実機ではこんな風に鳴るけども、オーケストラで演ったらこうなる、というのをコンサートで観せたりして。ゲームの枠を超えて音楽の啓蒙活動的なこともやられたりしていたと思います。
――技術的なところですと、音をずらしてディレイみたいな効果を生み出していたのが面白かったです。
あれは自分がバンドやってたりエフェクターの知識があったからだと思います。あと、音程をちょっとだけずらして2音同時に鳴らすと、少し音が膨よかになったり。当時はとにかくゲーム音楽を作る人はメーカーに少なくて、たまたま自分が音楽が好きだったから、それに繋がったのかなと思います。制約があったからこそいろんな工夫が生まれたと思います。
――昔はレコーディングもアナログテープで、編集するのもテープにハサミを入れるという覚悟がいるわけですけど、今はハードディスクで非破壊編集が当たり前になりました。Tanakaさんはこういった最新技術の音楽制作はどう感じていますか。
昔は本当に一発録りのレコーディングもあって、音に影響を与えるような緊張感があったと思います。けれどデジタルはデジタルで無限にトラック数が持てるとか、エフェクト技術の進歩で音にいろんな加工を施し、いままでに聞いたことないような音が生まれたり、それはそれで素晴らしいことだなぁ、と感じています。
――Tanakaさんはインストの他にもアニメ『ポケットモンスター』の主題歌など歌ものも制作されていますが、歌ものとインストでは向き合い方はどのように変わりますか。
歌ものは「言葉」があるから、全然違いますね。トラックを作る時もなるべく本人に仮歌を録ってもらって、ちゃんとその人の声に合わせてサウンドを組み立てるようにしていて。インストと歌もの、どちらが楽しいかといえば歌のバックを作っている時の方が自分は楽しいですね。あと、ポケモンの場合、多くのリスナーが子供である、という事は作編曲する上でいろいろ考えるキッカケを与えてくれました。
――子どもに受け入れやすいメロディというのもあるのでしょうか。
それはあまり意識せずにやっていました。自分の子供の頃の記憶を思い返すと、楽しい、元気、といったポジティブな感情だけでなく、儚い、切ないといったそれって大人じゃないとわからないんじゃないの?と言われそうな感情を音楽から受け取ってた気がしてて、そういう部分は素直にストレートに出した曲にしていきたい、と考えてました。それはポケモンの楽曲をお願いされた最初から思ってました。
――そういえば、11月8日に亡くなられてしまったドラマーの菅沼孝三さんは『ポケモン』の楽曲「OK!」で叩いてもらった事があるみたいですね。
彼は自分が10代の頃参加してたバンドと近しいバンドのメンバーでした。同じ練習場をシェアしてた時期もありました。東京に来てからはほとんど会ってなかったですけれど。『ポケモン』の曲で結構ハードなロックっぽい曲を考えた時「これはぜったい菅沼くん」だなと。で事前にアニメの曲だけどツーバスでやって欲しいとお願いしました。菅沼さんも「ほんまにええの?」なんてやりとりしていたのを覚えています。いまでも『ポケモン』ファンの人たちの中でも人気のある曲の一つです。
――Tanakaさんから見た菅沼さんのドラムはどんな風に映っていますか。
10代の頃からキックを両足を鳴らしたり、とにかくインパクトありました。当時から天才的なドラマーでした。けれど彼のドラムは昔から良い意味で変わってないと自分は感じています。彼は大阪で有名なジャズドラマーのお弟子さんだったと記憶しているのですが、いまでも10代の彼が叩くフォー・ビートの姿が目に焼き付いています。
――最後にTanakaさんはこれからどんな音楽にチャレンジしていきたいですか。
音楽の前にまず健康ですかね(笑)。自分の頭だけで音楽は作り出せなくて、その人の持つ身体性がすごく大事。20代、30代は基本健康なんですよ。でも僕は還暦を過ぎたし前提が違う。今作はコロナ禍であまり動けなかったから優しい曲が多くなったみたいに、自分が置かれた環境に影響を受けることがすごく多い、また良い曲をたくさん聴いたから良い曲が作れることも絶対ないですし。なのでまず身体、食べ物含め気にしたいと思っています(笑)。あと世の中あらゆる場所でどんどん変化が起こってる時期だと感じています。生きづらい、とか反感持つ部分も増えていくと思うのですが、そこは正直に生きていきたいし、そんなギクシャクした気持ちを抱えながらも、多くの人に少しでも聞いてもらえる音楽を生み出していけたら、と思っています。
(おわり)
- 1
- 2